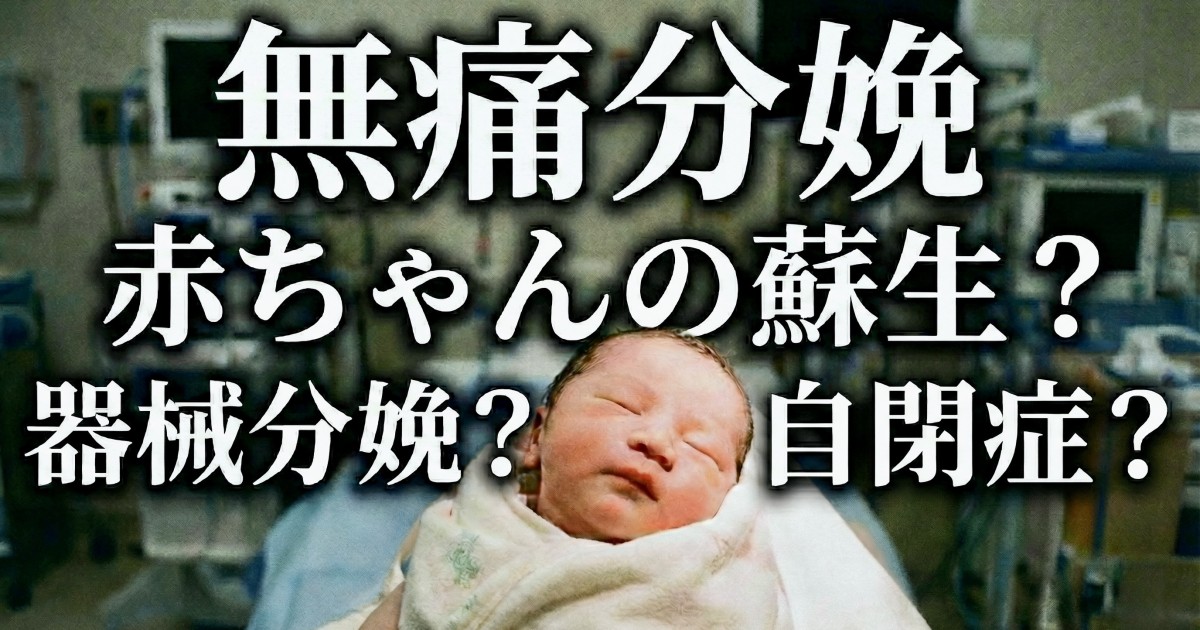映画「たしかにあった幻」河瀨直美監督と語る子どもの臓器移植問題
2月も始まりましたね。
寒い冬ももうすぐ終わりです。早い所だと梅の開花も見られるのではないでしょうか。
今回も大好評・対談シリーズです。
今回は「たしかにあった幻」という映画(2/6公開予定)の河瀨直美監督とInstagramで対談したので、その対談の様子を紹介します。
ふらいと先生のニュースレターは、子育て中の方が必要な「エビデンスに基づく子どもを守るための知識」をわかりやすくお届けしています。過去記事や毎月すべてのレターを受け取るにはサポートメンバーをご検討ください。
2/6金曜公開:映画「たしかにあった幻」

フランスから来日したコリーは、日本における臓器移植への理解と移植手術の普及に尽力するが、西欧とは異なる死生観や倫理観の壁は厚く、医療現場の体制の改善や意識改革は困難で無力感や所在のなさに苛まれる。また、プライベートにおいても屋久島で知り合った迅と同棲を始めるが、お互いが使う時間のズレからくるコミュニケーションの問題に心を痛めていた。そんな中、心臓疾患を抱えながら入院していた少女・瞳の病状が急変するが・・・。
「幻」とは実在しないものがあるかのように見えること、あるいは存在自体が疑わしいもの、の意に相当する。それを修飾する言葉として「たしかにあった」という表現は、論理的には成立しない。にもかかわらず、相反するワードを敢えて同義的に並べたタイトルは、二項対立を超えてゆく新しい思想を提案する本作の内容を知らしめている。また、この映画は、河瀨直美監督にとって6年ぶりとなる劇映画の最新作でもあり、オリジナル脚本としては8年ぶりである。物語を支えるテーマは二つ。一つは、先進国の中でドナー数が最下位という日本の臓器移植医療について。もう一つは年間約8万人にのぼる日本の行方不明者問題だ。河瀨監督は『あん』(15)で差別と偏見の果てに生きる歓びを人々に与えたハンセン病患者の生き様、『光』(17)で失われゆく視力に翻弄される人生の中で気づかされた新たな愛を獲得したカメラマンの人生、『朝が来る』(00)では特別養子縁組で救われた命の尊さと二人の母の絆など、旧来の常識や血縁とは異なる、他者との関係性の中に存在する「愛」を描いてきた。「死」が終わりではないという気づきの先に、移植医療が人の命を繋いでゆき、「生」の意味を問いかける本作は、第78回ロカルノ国際映画祭でのワールドプレミア上映にて、河瀨監督のマスターピース(傑作)と評された。
河瀨直美 監督

生まれ育った奈良を拠点に映画を創り続ける映画作家。一貫した「リアリティ」の追求はドキュメンタリー・フィクションの域を越えてカンヌ映画祭をはじめ、世界各国の映画祭での受賞多数。代表作は『萌の朱雀』『殯の森』『2 つ目の窓』『あん』『光』『朝が来る』など。 世界に表現活動の場を広げながらも、2010年には、故郷・奈良にて「なら国際映画祭」を立ち上げ、後進の育成にも尽力。ユネスコ親善大使、奈良県国際特別大使を務めるほか、大阪・関西万博ではテーマ事業プロデューサー兼シニアアドバイザーを務めた。 俳優として、第 38 回東京国際映画祭最優秀女優賞を受賞する他 CM 演出、エッセイ執筆など、ジャンルにこだわらず活動中。 プライベートでは、10年以上にわたりお米作りにも取り組んでいる。
背景:子どもの心臓移植問題の現状
日本の子どもの心臓移植をめぐる問題は、「移植医療の技術があるのに、必要な人に届きにくい」という供給のボトルネックに集約されます。心臓移植は脳死下の臓器提供を前提とする医療ですが、日本の脳死下臓器提供は2024年で130件にとどまり、そもそも提供数が限られています[1]。その結果、移植を待つ時間が長くなり、待機中の治療や家族の生活にも重い負担が積み上がります。
とくに子どもは、体格や血液型などの条件が合う「小さな心臓」が必要になるため、供給不足がより深刻になります。日本臓器移植ネットワークの集計では、18歳未満からの脳死下臓器提供は2010年7月〜2024年12月の累計で92件、2024年単年では11件です[1]。一方で、脳死下で実施された心臓移植は2024年に111件(累計930件)とされ、必要性に比べて提供が十分とは言いにくい状況が続きます[1]。また、提供の多くは「本人の意思表示」ではなく家族の承諾によって成立しており、2024年は家族承諾107件、本人意思表示23件と報告されています[1]。つまり現場では、突然の出来事のなかで家族が非常に重い決断を迫られる構造がある、ということでもあります。
待機の長期化は数字にも表れています。厚生労働省資料(日本臓器移植ネットワーク公表値の引用)では、心臓の移植希望登録者は2024年12月31日時点で821人、登録後に亡くなった方は累計608人と示されています[2]。重症心不全では補助人工心臓(VAD)などで「移植までつなぐ」治療が発達してきた一方で、待機そのものが年単位に延び、成人のStatus1では平均待機期間が2022年に1,877日(約5年)と報告されています[3]。子どもの場合も、待機中にVADなど高度な循環補助を要するケースが少なくなく、医療者側にも家族側にも、長期にわたる緊張と負担が生じます[4]。
一方で、ここはきちんと押さえておきたい希望でもあります。国内の小児心臓移植は成績が良好とされ、法改正後2022年末までに移植時18歳未満の68人が国内で心臓移植を受け、移植後5年・10年生存率はいずれも96.2%とまとめられています[4]。つまり「救える可能性が高い」からこそ、救命につながる臓器提供が追いつかない現状が、社会全体として重い課題になっています。今回の映画で言える社会課題は、特別な誰かの話ではなく、このギャップの上で日々起きている現実といえます。
参考文献:
[1] 日本臓器移植ネットワーク「脳死臓器移植の分析データ」(2024年12月31日現在)
[2] 厚生労働省資料「臓器移植希望登録者の現況(2024/12/31現在)」※JOTN公表値の引用
[3] 日本心臓移植研究会「日本における心臓移植報告(2023年度)」
[4] 日本移植学会「臓器移植ファクトブック2024」

「たしかにあった幻」を医療者側から見る
今西: 本日はよろしくお願いします。
河瀨: よろしくお願いします。では、今回は映画を見ていただいて、率直な感想を聞かせていただいていいですか?
今西: はい。もう2回見させて頂いたんですけど、まず映像として映像が綺麗だなと思いました。その前に自己紹介をすると、小児科医で、新生児科といった赤ちゃんを専門にした医者をやってます。今は臨床を離れて、米国のロサンゼルスの大学で子供の医療政策の研究をしています。今ちょっと一時帰国中です。
河瀨: 都内のホテルからインスタライブをしてるんですよね。
今西: そうですね。元々は医療漫画の『コウノドリ』という、ドラマにもなった作品があるんですけど、大森南朋さんだとか綾野剛さんとか、そういった方々と一緒にもお仕事をした経験があります。
河瀨: え、ありがとうございます。
今西: 『コウノドリ』って周産期医療なんですよね。なので結構、人が生きたり死んだりっていう現場でもあるんです。僕も医療の映像化というのに携わった経験があり、その立場から監督の作品を見させていただいて、非常に自然が豊かに描かれていて、緊張とリラックスがいい具合に映像として表現されているなと感じました。
今回、子どもの臓器移植というテーマでしたけど、僕も小児医療に触わってたんですけど、非常にいい話だけじゃないんですよね。いわゆる医療者のドロップアウトも大きくて、医療者の心理的負担も大きいんですよね。若い世代はみんな辛くて辞めていったりとか、ダイレクトに子供の生と死が直面する現場なので、我々の心理的負担が大きいです。その葛藤が忠実に描かれてるなっていうのを、率直な意見として感じましたね。
河瀨: ありがとうございます。この葛藤と言われた部分は、主人公のコリーちゃん(※役名)が海外の目線として体験していて、プライベートも含めて自分の感情をコントロールしていかなきゃいけない立場にあるんですけど、そこの部分でも「人」という性格であったり、パートナーさえもそこで自分の感情をプライベートに持ち込んじゃってうまくいかない、みたいな感じのところがあったんですけど。 私も今回取材を通して、本当の小児科医の先生とか取材させてもらってるんですけども、本当に寝てても呼び出されれば飛んでいくみたいな感じの先生もいらっしゃいますし。一つの命を救うために、もう3日間ずっと付き添ってるとか、そんな話もよく聞くんですけど。これって、先生今海外に行かれてると思うんですけど、欧米の状況は少し日本の状況とは違うものなんですか?
今西: そうですね。あちらでは研究職なんで現場っていうのは協力って形でコラボレーションしてるんですけど、一番海外と日本で医療現場として違うなと思うのは、働くスタッフのメンタルヘルスっていうのを米国では重要視してるっていうことですね。
河瀨: そうですね。
今西: 日本はいわゆる「72時間付き添い」とか、そういったパターナリズム的な、医者だったらそういうのが当たり前だよねっていう雰囲気がありました。今は変わってきたんですけど、その医者の自己犠牲の元に成り立っている医療ってのは結構あってですね。 なので、私自身も赤ちゃんとか子供の死で、自分の患者さんが亡くなるっていうのは結構メンタルヘルスが損なわれるという事を経験しました。そういう葛藤があの映画を通じてそのまま忠実というか、自然との比較が綺麗に出ていて。葛藤を思い出しながらちょっと自然に涙しそうな感じで、色々考えさせられましたね。
河瀨: ありがとうございます。コメントも素敵なのを頂いているんですけど、何回も見たっていう風に言っていただいてますし。
そういうリアリティのところを言っていただいてるんですけど、日本の課題ってあると思いますし、養子縁組に関する考え方もなかなか日本ではそれそのものを語るっていうことがあまりないですね。もっと引いたところで言えば、「死」という命だったりということを、テーブルに乗せて議論するみたいなところがあんまりないんですよね。
忌み嫌うというか、死に対してはそれが全ての終わりだっていう風なことだったりとかする中で、私はその「命のバトン」というか、そういうものを一つ描くっていうことで、ただ失う側のドナーの人の姿っていうのも同時に描いていくことで、そこにある葛藤みたいなものを全部とは言えないかもしれないですけど、私が取材してきたものの中のあらゆる側からの視点をリアリティを持って描いたつもりなんですね。
だからその時に多分お客様が感じる事は、あのクエスチョンに対するアンサーを皆さん色々出し始めると思うんですよね。全く語られなかったこととか、そういうことなんだなっていうようなことを、考えるきっかけにしてもらえたりもできるといいなと思ってたんです。
映像の「解像度」ー徹底されたリアリティ
河瀨: 日本はどうしても一つの価値観のところで、そこから外れるものを排除する文化でもあるんですけど、海外だといろんな方たちが同じところに暮らしたりする中で、あらゆる考え方もあって一つのルールが決まっていく所もあるのかなと思います。だから先生がそういう風に見られた時に、この一つの課題を、この映画が見られた時にどういう風に見て思われましたか?
今西: そうですね。僕は医療現場に普段いるので、医療現場の中で本当に起きていることをリアルに見ている感覚になりました。 僕、医療に漫画やドラマの取材協力をさせてもらった立場で、いろんな医療ネタを扱った映像って見るんですけど、『コウノドリ』もそうなんですが、リアリティを突き詰める方向の映像化か、あるいはその医療をエンターテイメントとして扱う方向性の映像化かっていうのはかなり違うと思っています。
今回の作品は現実に近い、医療の現場を本当に忠実に描かれてるなっていう印象を持ちました。 ここまで持ってくには、制作のスタッフも、ある程度「解像度」を上げていかないとあの境地には達しないだろうなっていうのがあって。監督も俳優さんも含めて努力は相当されたんじゃないかなっていうのが、映像を見て感じました。
河瀨: うん。先生からそう言っていただけると、私たち作り手としては感慨深いものがあります。実は「河瀨組」って言うんですけど、本当にリアリティを追求していく集団だと自負しています。例えば今回は小児なので小児病棟を作るんですけど、もうそのまま明日から小児医療をここでやってもらうぐらいリアリティのある現場を美術が作ってるんですね。
コリーちゃんの机の引き出しを開けると、クリップとかペンとかもそのまま入ってたり、見えるところ以外のものも全部リアリティを持って作ってる。
あとそういう風にすることで、俳優さんがもうまるでそこで本当に自分が医療従事者になってるような、そういう感覚を得てもらう方向に作用しています。実は私たちスタッフ全員白衣着たり、医療従事者の格好して撮影してたんですよ。
今西: メーキング上がってて見ました。あれで、かなりの打ち合わせが必要で、かなりの解像度を上げてらっしゃるなっていうのは分かりましたね。
河瀨: 先生、その「解像度」っていうのは、見ていただいてる方に向けて言うと、その輪郭とかがはっきりするとか、そこにアバウトな、なんていうかギザギザを出さないというのか、そういう感じでしょうか?そのクリアにというか。
今西: はい、そうですね。なんで例えば医療関係者が見ても違和感のないぐらい、こう現実というか本当に医療の現場にいるような感覚になります。さっきおっしゃった映像にも映らないようなものも含めることを指しています。例えばコウノドリだったら点滴のメニューまで、多分全然映んないんですけどそういうのも細かく作ったりとかしていました。そういったことで俳優さんたちが現場に溶け込むというか打ち込めるような環境作りっていうのは、かなり大事なんじゃないかなという気はしました。
河瀨: そうです。あの子供ちゃんもね、自分の病室から出る時は、点滴みたいなのを持って、そういうのが体にもうついてるようにしてるんです。それ持ってじゃないと動けないし、だから動きも制限されるし。院内学級に行く時だけ自室を出て行くとか。そこにあるものも、本から何から全部そのままのものだったりしました。ご飯もロケ弁のようなケータリングなんですけど、それをお部屋に持っていって、お部屋でそれぞれに食べてもらうっていう感じにしていました。
そうする事で、普通の生活が自分の自室で行われたり、大部屋だったら大部屋でいつもいる子が一緒にいたりしてもらいました。映画には出てない子たち、一瞬しか出てない子たちもいるんだけど、ある程度の数のお部屋にちゃんと子供たちが入院してるんですよね。 ナースステーションにも、出番がなくても看護師の皆さんがそこにいたり、事務の人がいたり、電話が常にかかってきてるようなことをやってたりとか。
そういうものがきっと、子役の子たちにも、ある意味そこで本当に生きているかのようなリアリティを与えていたと思うんです。
死は「敗北ではない」ーカンファレンスシーン
河瀨:先生、カンファレンスのシーンとかディスカッションのシーンはどうでしたか? 例えば最後の心臓移植のシーンだったりとか。
今西: あのシーンは印象に残っています。僕らも緊迫した雰囲気で意思決定をしているなっていうところがちゃんと出てるなと感じました。
つまり移植決定、そして移植実施までのプロセスが、いろんな葛藤を経てたどり着いていくという、いわゆるシステムとして動いているのが、僕らにとっては本当にリアリティがありました。 自分も年間10人ぐらい赤ちゃんとか子供たちを看取ってるんですけど、当然医者として子供を生かしたいというのは当たり前なんです。
しかし同時に、残された時間を家族として有意義に過ごしてもらうためにどうしていくかっていうのを、心理士さんとかソーシャルワーカーさんとか、臨床工学技士さんとか、多職種を入れて様々な価値観をぶつけ合いながら一つの結論に達していくんです。
最近は他の医療施設などでは、ご家族をカンファレンスに参加させて意思決定を一緒にしていくってことも欧米ではやられているんですが、そういった現実的な葛藤が描かれてるってのがカンファレンスにありました。時間がないので病状が進行していく時間に急かされながらも、葛藤を通じて一つの結論に達していくというのが描かれてて良かったと思います。僕はあのカンファレンスのシーンが一番心に響きました。
河瀨: そうですね。
カンファレンスシーンは3つほどあるんですけど、最初はコリーちゃんが「なぜ死の定義が違うのか」という議論するシーンです。日本は心臓死だけど、脳死が人の死ではないというところなどをどうして語らないのか、そこに課題があるのだとしたら、どうしてそこに乗らないんだと言って「この現状を知ってもらわなきゃいけないからビデオ撮らせてくれ」と言うシーンですね。
2回目は、そのビデオを撮ってきて見せるんシーンなのですが、日々の医療に忙しい現場は理想の課題を持ってこられてもなかなか向き合えない現実がある事を描きました。一人の方にものすごい負担がいってたりとかする現実が見えてくる。一生懸命、証拠みたいなものをコリーは海外の目で撮りためるんだけど、それを構っていられない現場を描いて。
そして3回目では、いよいよドナー家族とレシピエント家族、本物の方なんですけど、それから脳外科医や心臓外科医、小児科医、厚労省の方もいらっしゃって、コーディネーターの方とか、これだけの座組の方々が一堂に会して移植のことについて議論しました。このシーンは我々のオリジナルのシーンですが、実際今の日本の現状ではないらしいんですよね。
実は実際6時間にわたってお話をしていただいたんですけど、使っているのは5分ぐらいなんです。私がこれまで取材してきた人たちに集まっていただいて、本当に忌憚なき意見で、シナリオもないところで3つのカメラを置いて撮りました。
私も息ができないような感じで、固唾を飲んで見守ってたんですけれども、その最後のカンファレンスシーンで、救急医療から今地域医療されてる先生が言われた言葉があります。まだ臓器移植がテレビ報道とかでわーっと騒がれていた時代に、脳死であるということが分かり、実際にまだ動いてる心臓を止めるという時に、すごくどうしていいかわからない気持ちにはなったけれど、運ばれた先でまた鼓動が始まったっていうのを聞いた時に、「死は終わりじゃないんだ」って先生が言われるんですよね。 あの言葉が、私はすごくこの映画の一番大事な部分なんじゃないかなと思ったんですけど、先生はどう思われましたか?
今西: はい私もあれは一つのキーワードになるんじゃないかなって思って映画を見ていました。僕たちの新生児医療の界隈ですと、上級の先生とか、新生児医療を何年もやって何百人も看取ってらっしゃった先生がよく言ってたのは、「死は敗北じゃない」って言葉なんですよね。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績