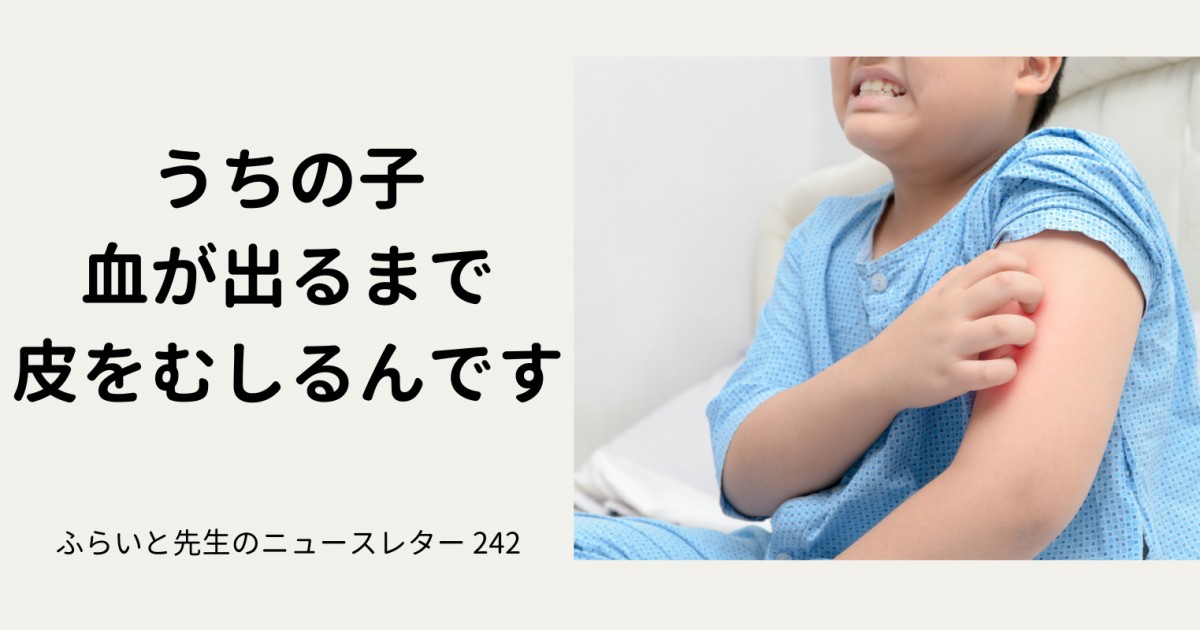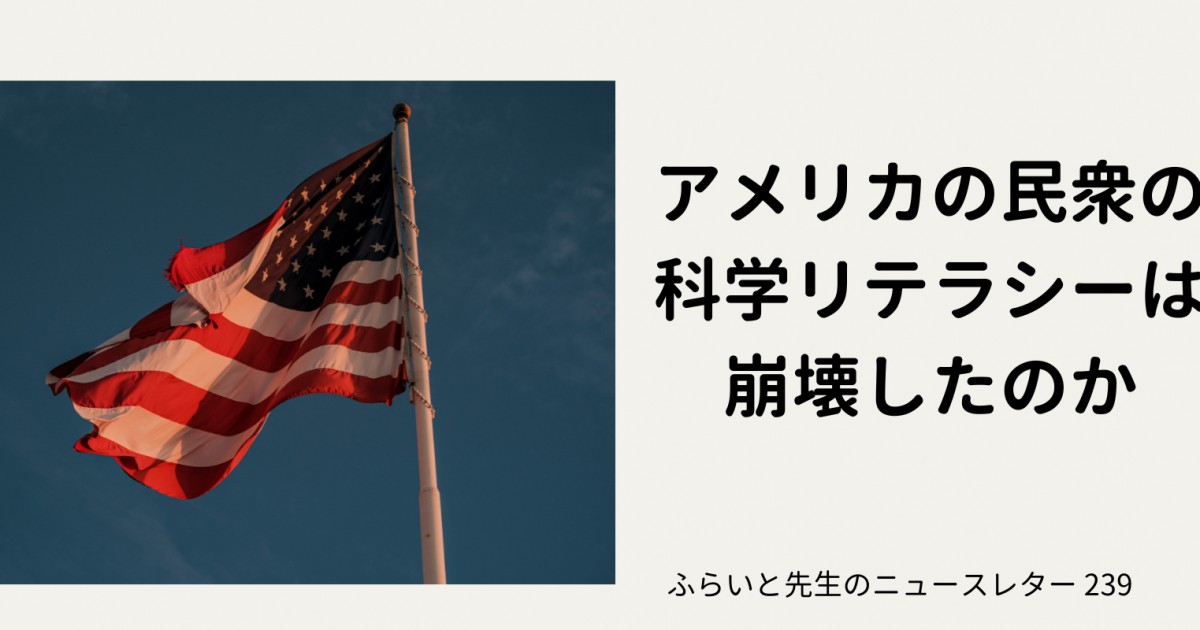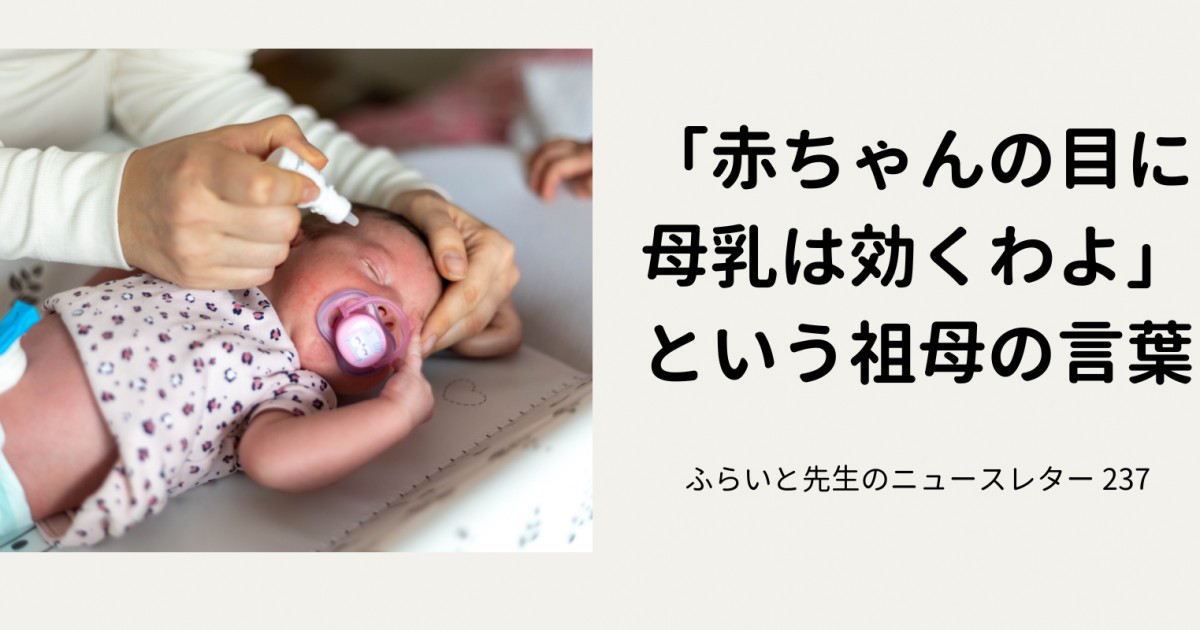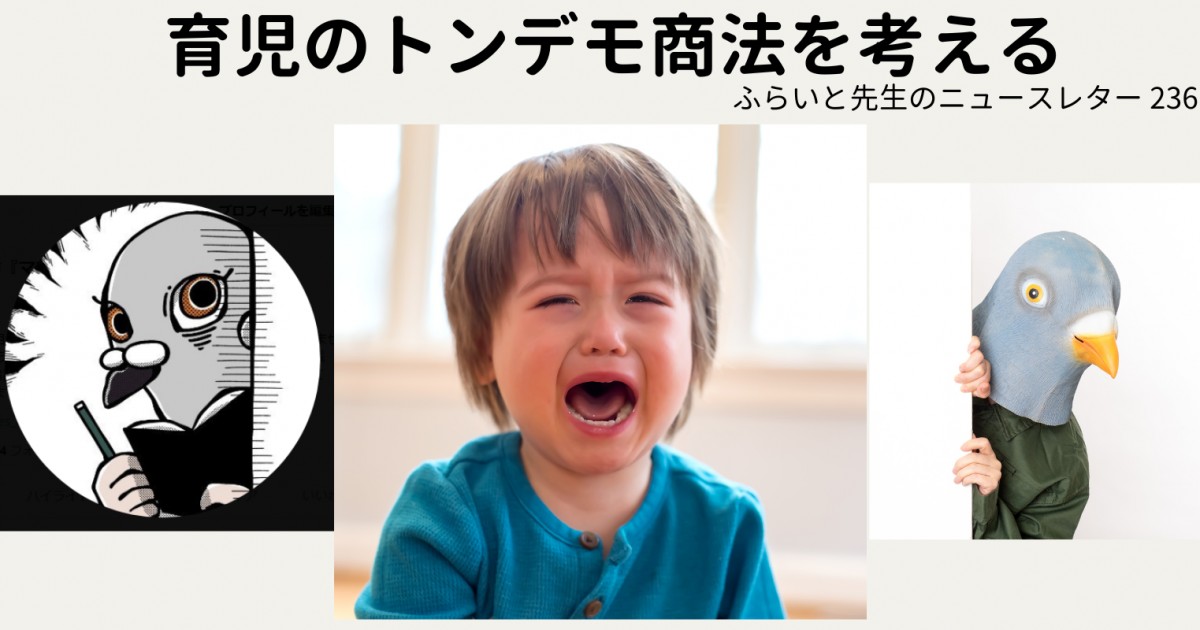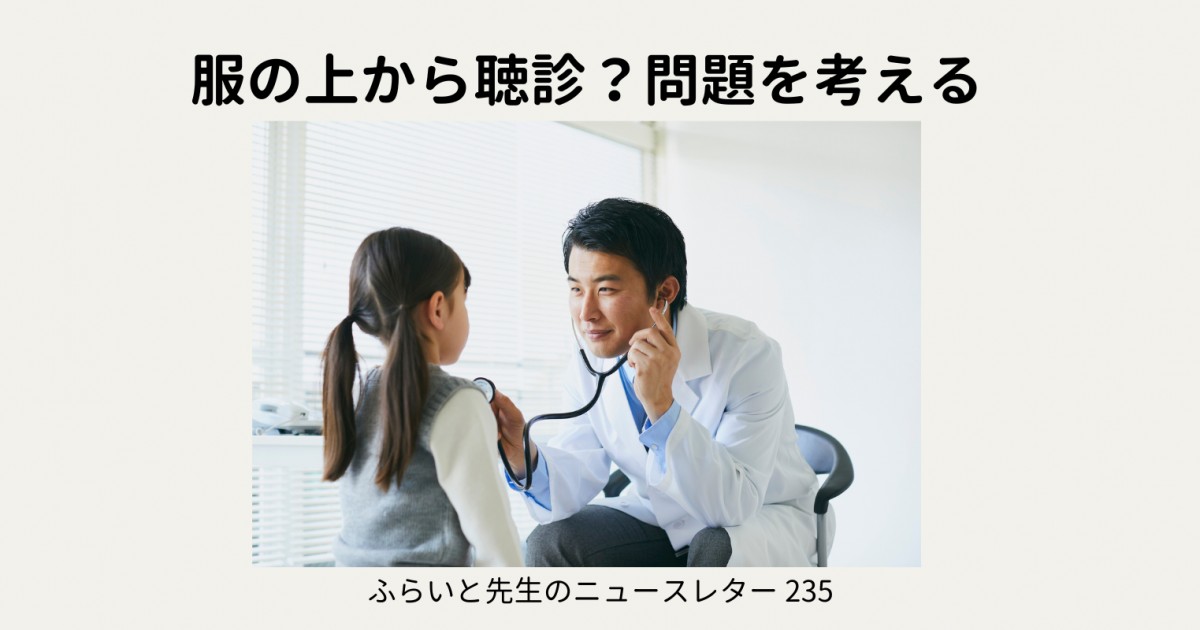夫婦げんか後に子どもをどうフォローするか
皆さん、こんにちは。
今月も7本目のニュースレター記事です。
米国でも娘達が夏休みに入り、夏休みの中でも忙しく過ごしています。特に長女と次女に毎日それぞれ1時間ずつ隣についてみっちり見ています。親としてはなかなか負担が大きいですが、渡米中だからといって特に数学は疎かにできません。親も頑張るのみです。
ふらいと先生のニュースレターは、子育て中の方が必要な「エビデンスに基づく子どもを守るための知識」を、小児科医のふらいとがわかりやすくお届けしています。
過去記事や毎月すべての「エビデンスに基づいた子どもを守るための知識」を受け取るには有料コースをご検討ください。今回の記事も登録いただければ最後まで読めます。
いつもありがとうございます。夫婦喧嘩の子供に与える影響について伺いたいです。良くないのはもちろんですが、どのような影響があるのか。また、子供の前で喧嘩してしまったときの、子供に対する後からできるフォローの仕方を知りたいです。第二子が生まれて喧嘩が増えてしまいました…気をつけてはいるのですが、子供の前で争ってしまうことがあります。
ご質問ありがとうございます。まずは育児、本当にお疲れ様です。
2人目の子どもが生まれたことで育児のタスクも増えてケンカする機会も増えますよね。
自分は思い返せば長女が生まれた時が夫婦げんかが1番多かった気がします。価値観が合うなと思って結婚しましたが、育児に関してはこれだけ価値観がずれていたのは実際に育児をしていて意外な所でした。
特に覚えているのが長女が赤ちゃんの時に泣いている時の対応です。自分は普段赤ちゃんが泣いている中で仕事をしているせいか、赤ちゃんが泣いていても可愛い可愛いとあやすだけでしたが、妻はなんとか泣き止ませようと、泣く原因をとことん追求しようと必死になっていました。泣いててもいいじゃない?と言うと、良くけんかになってました。
あの時の自分の言い方も悪かったですが、あれから8年経過した三女の時は妻もその追求も肩を抜く形でアジャストしていったようです。いい意味で、「赤ちゃんは泣くものだよね。けどここからは介入しよう」という意識が夫婦間で自然と出来上がったのかなと感じています。まあケンカが激減したのはお互い歳を取ったのが大きかったですが。。
それでも今でも子どもの前でケンカしてしまう事があります。気をつけていても子どもの前で争ってしまうことがあるというのは、多くのご家庭が経験する非常によくある悩みです。
しかし、決してご自身を責めないでください。
実はこれは科学的にも裏付けられた現象なのです。
アメリカで行われたある研究では、241組の夫婦を対象に第二子の誕生前後を追跡しました。その結果、第二子が生まれた後、夫婦間の「共同育児(coparenting)」における対立は有意に増加し、協力関係は逆に減少することが明らかになりました(#2)
相談者さんが今感じている困難は、実は個人的な問題でなく、多くの家庭が経験する構造的な変化であることを示しているのです。またこの時期は、第一子の赤ちゃん返りや情緒不安定(不安、攻撃性、引きこもりなど)が起こりやすい事もわかっています。
このような家族の変化が起きる夫婦間の対立は、ある意味で自然な事なのです。
しかし、ここで重要なメッセージがあります。
それは、子どもにとって有害なのは、夫婦間に意見の対立があること「そのもの」ではないということです。本当に子どもの心に影響を与えるのは、そのケンカの「質」(どのように喧嘩するか)、そして何よりも、喧嘩の後に「和解と修復」があるか、という点なのです。
もし子どもの前でケンカしてしまった時に、そのダメージをどのように最小限に抑えるかを重点的に解説していきましょう。
なぜ夫婦げんかは子どもの「心の安心」を揺るがすのか
子どもにとって、家庭は何よりもまず「心の安全基地」です。この基地が安全で、安定していると感じられることは、子どもが健やかに発達していく土台となります。夫婦喧嘩が子どもに与える最も深刻な影響は、この安全基地そのものを根底から揺るがしてしまう点にあります。
これを説明する上で大切なのが「情動的安定性理論」です。
この理論では、子どもには「家族という単位の中で、情緒的な安全性を維持したい」と本能的な願望があると説明されています。
逆に家族内で情緒的な不安定さがあると、親の対立と子どもの長期的な心の問題とを結びつけてしまう「仲介役」になってしまう可能性が複数の研究で言われています。
例えば、アメリカで228家族を対象に行われたある長期的な追跡研究(#2)では、学童期初期に夫婦間対立が激化していると、なんとその5年後、子どもが思春期になった時の「情動的不安定性」が増加することがわかりました。
さらに衝撃的なのは、同じくアメリカで232家族を8年間にわたって追跡した別の研究(#3)です。この研究では、幼少期の破壊的な夫婦喧嘩が、学童期の「情動的安定性」の低下を介して、思春期における不安や抑うつといった内面化問題を引き起こすという、長期的な因果の連鎖が明らかにされました。
これらの研究は夫婦げんかの影響が長い時間、子どもの心に深く影響を及ぼしている証拠になります。
そして、これらの悪影響は心理的なものに留まりません。
研究によれば、生後6ヶ月の赤ちゃんでさえ、両親の怒鳴り声を聞くと、心拍数が上昇し、ストレスに関連する脳の領域の活動が高まるなど、生理的なレベルでの苦痛反応を示すことを示した研究もあります(#4)こんな小さな赤ちゃんにも夫婦げんかがバイタルサインとして現れるというのは、いかに子ども達にとってリアルな危険として感じられるかを意味します。
夫婦げんかの「スタイル」で子どもへの影響は違う
ただ、すべての喧嘩が等しく有害なわけではありません。
研究では、喧嘩の「スタイル」によって、子どもへの影響が天と地ほども違うことが明らかになっています。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績