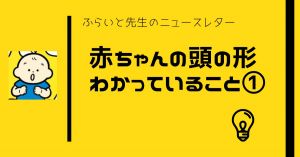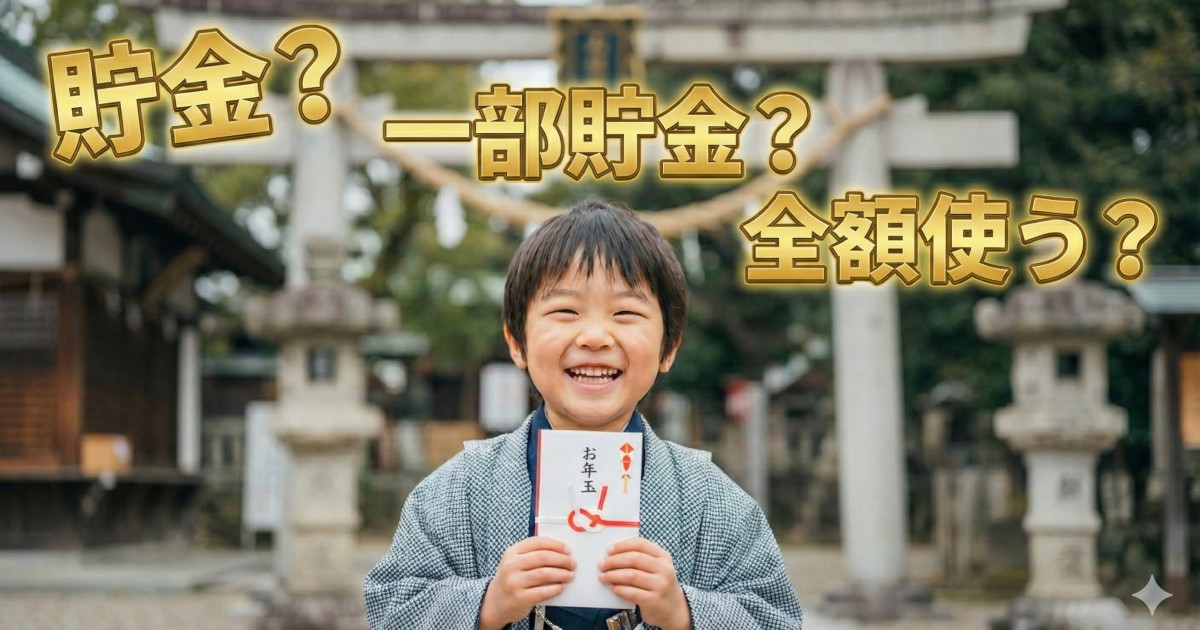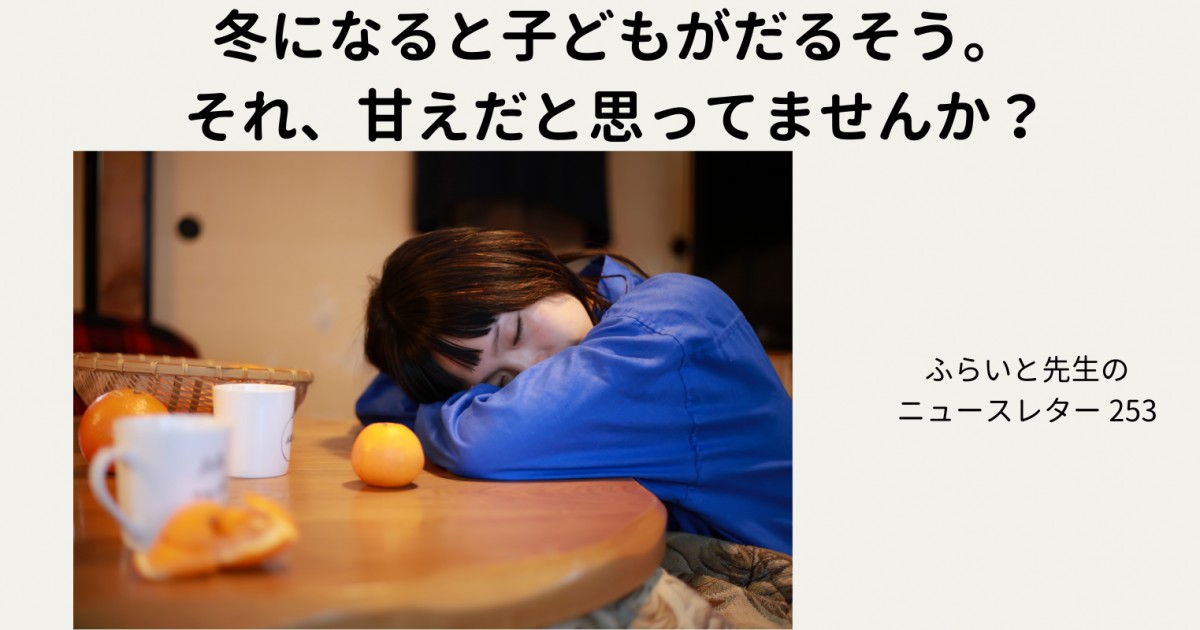シン・赤ちゃんの頭のカタチ2025
皆さんこんにちは。9月ももう終わりですね。
というかあと3ヶ月早すぎませんかね。ついに2026年の足跡が聞こえてきました。ところで来月は、このニュースレターを始めて3周年になります。
来月あたり一度区切りとした記事を書いてみようと思います。
今回は最近質問が増えてきた赤ちゃんの頭の形です。過去にも一度取り上げたことがあるのですが、あれから3年弱経過しているので一度ここで最新版にしたいと思います。あとあそこでは語れなかった我々新生児業界での「赤ちゃんの頭の形」はどんな位置付けなのかも触れたいと思います。
ふらいと先生のニュースレターは、子育て中の方が必要な「エビデンスに基づく子どもを守るための知識」をわかりやすくお届けしています。過去記事や毎月すべてのレターを受け取るにはサポートメンバーをご検討ください。
少し驚いた訴訟

「助産師指導で頭部変型」女児と両親が高知市提訴 4243万円賠償請求」 kochinews.co.jp/article/detail… 助産師指導で頭部変型 女児と両親が高知市提訴 4243万円賠償請求 | 高知新聞 高知市の産後ケア事業で派遣された助産師の「硬い布団で寝かせるべきだ」という指導に従った結果、女児(2)の後頭部が平らに www.kochinews.co.jp
少し前にちょっと驚く裁判がありました。
高知県高知市で、生まれてきた赤ちゃんに産後ケアで派遣された助産師さんがその時点で乳幼児突然死症候群(SIDS)を防ぐため「硬い布団で寝かせるべきだ」という指導を行いました。
その指導に従った結果、2歳の女児の後頭部が平らに変形したとして、22日までに、市と助産師、県助産師会が4243万円の損害賠償を求める訴訟を起こされました。
ネットの反応では
「命より頭の形が大事なのか」「これでは何も指導できなくなるね」
とおそらく助産師さんや保健師さんだろうアカウントがSNSで色んな声をあげていました。
自分は基本的に自分のXの投稿へのリプライや引用を見ない(というか見る時間がない)ので、自分の投稿にも寄せられているかもしれません。
あとこれは繰り返しどこでも言っていますが、報道内容だけでは状況がわからないので本件に関するコメント、これ以上は差し控えたいと思います。

一方、とにかく昨今の赤ちゃんの頭のカタチに対する世間の盛り上がりは、本当ここ5年ほどで凄い勢いだなと感じています。
以前にも、頭のカタチに関してはこのニュースレターでも取り上げましたがもうすでに3年の月日が流れているので、改めて書き直そうと思い立ちました。
リアルでもSNSでもよく聞かれる事が増えてきたので、今の日本の現状を鑑みて、数少ない日本周産期新生児専門医の1人として申し上げておくと、私自身の個人のスタイルとしては「反対するものでもないし、強くオススメするわけでもない。したい人はしたらいい」というものです。
これには、新生児医療業界の中でも多大な議論が起きているという背景があります。
それでは私がなぜそう思うのか、現時点で科学的にわかっていること・わかっていないことをまとめたいと思います。そして最近、新生児業界で感じることも述べていきたいと思います。
赤ちゃんの頭はなぜ変形するのか?
赤ちゃんの頭の骨は、産道を通りやすくするため、そして生まれてからの急速な脳の成長に対応するために、とても柔らかく、いくつかの骨がパズルのように組み合わさっています。
この骨と骨の間には「縫合」と呼ばれる隙間があり、生後しばらくは完全にくっついていません。この「柔らかさ」こそが、赤ちゃんの頭が変形しやすい主な理由と言われています。
頭の変形、すなわち「位置的頭蓋変形症」は、病的なものではなく、持続的な外からの圧力がかかることで生じます。
では、なぜ圧力がかかってしまうのでしょうか。
最大の理由は、1990年代から世界的に推奨されるようになった「仰向け寝」です。
これはSIDSのリスクを劇的に減らした非常に重要な育児指導ですが、赤ちゃんが長時間同じ方向を向いて寝ることで、後頭部に圧力が集中しやすくなりました。いつも同じ方向を向いてしまう「向き癖」も変形を助長する大きな要因です。
また、生まれつき首の筋肉にしこりや硬さがある「筋性斜頸(きんせいしゃけい)」があると、赤ちゃんは楽な方にしか首を向けなくなるため、斜頭症を合併しやすくなります。その他、多胎妊娠でお腹の中が狭かったり、骨盤位(逆子)だったりすることも、出生前の要因として知られています。
重要なのは、これらの変形の多くは成長とともに改善する機会を得るように発達していく、ということです。首がすわり、お座りやハイハイをするようになると、寝ている時間が減り、頭に均等な力がかかるようになります。脳が成長して内側から頭蓋骨を押し広げる力も、形を丸くするのに役立ちます。
しかし一方で、それだけでは治りにくい頭蓋変形もいました。そこで出てきたのが「ヘルメット治療」です。
効果があるとされたヘルメット治療の議論
こういった赤ちゃんの頭蓋変形に対してヘルメット療法は「形を整える」目的で広く使われてきました。確かに多くの比較研究では、ヘルメットを使用すると治療中〜治療直後の形の指標が改善しやすいことが示されています。直感的にも、頭の形が変化しやすい(骨がまだ融合していない)状態で、成長に合わせて隙間を設けたヘルメットで頭の成長方向を誘導すれば、短期的に形が良くなるのは不思議ではないでしょう。
紹介したい研究は、オーストラリアの研究者らによって2021年に発表されたものです(#1)
18本の研究を分析し、ヘルメット療法は、体位変換などの保存的治療と比較して、頭の形の非対称性を改善させる上で統計的に有意な効果があると結論付けています。
この検討に含まれた研究の多くが、ランダム化した研究ではなく、治療をしたグループと、歴史的なデータや別の集団を比較するような「観察研究」であった点です。観察研究では、もともと重症な子がヘルメット療法を受け、軽症な子が経過観察になる、といった偏り(バイアス)が生じやすいため、この結果は慎重に解釈する必要があります。
また、2025年に発表された複数の研究を検討したメタ解析でも、非ヘルメット療法(自然経過やリポジショニングを含む)と比較した13研究・1189人を統合したところ、短期の頭形指標(CVAIなど)の改善はヘルメット群の方が大きいという結論でした(#2)
また以前の記事でも指摘したように、頭蓋変形は全身へ様々な二次的な影響が出る(・顎関節偏位からの噛み合わせの悪さ・耳介偏位による中耳炎・肩こり、偏頭痛、側湾症、腰痛・耳の高さが異なり眼鏡がズレてかけられない・顔が歪んでコンプレックス)という事も変わらず指摘されています。
ただし、皆さんが知りたいのはそこではないでしょう。親や医療者が本当に知りたいのは「長期的に目立つ差が残るのか」「学齢期の見た目や生活のしやすさに差が出るのか」「発達や学業成績のような神経学的な長期アウトカムが良くなるのか」といった点です。
このヘルメット治療に関して最初に世界的に議論を巻き起こしたのが2014年にオランダの研究チームによって発表された研究です(#3)。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績