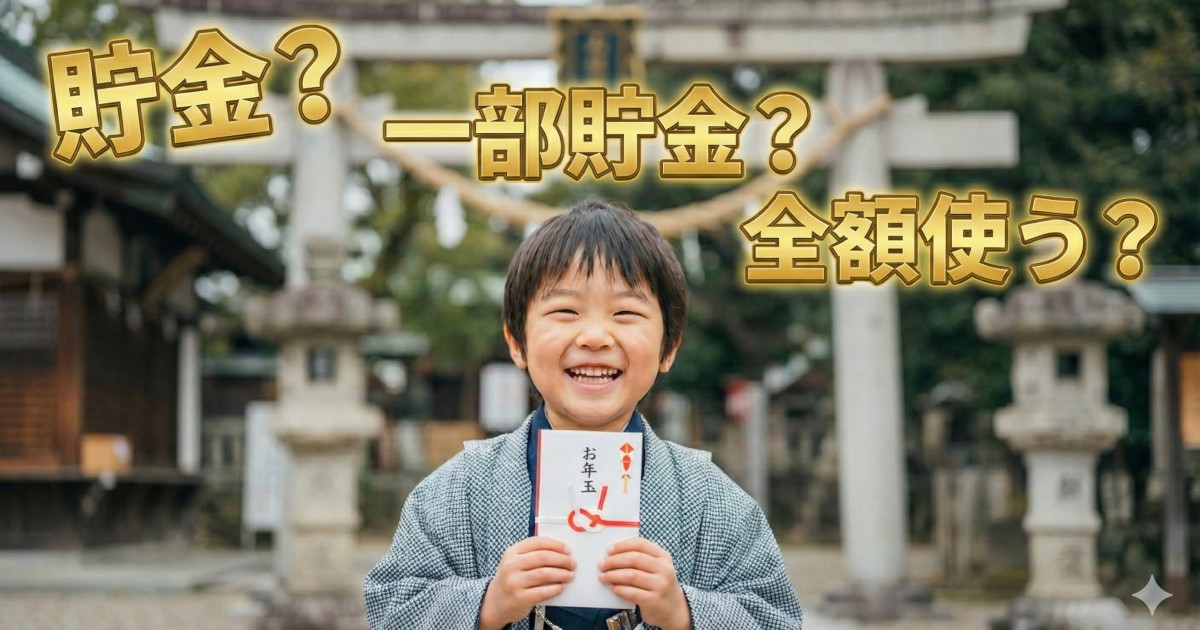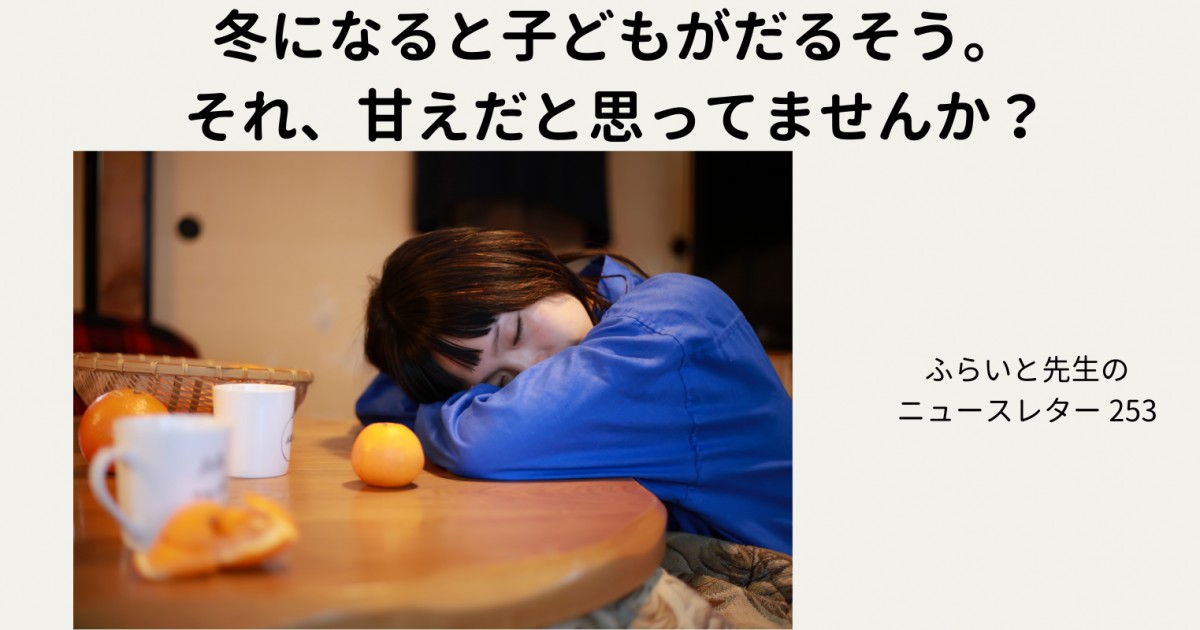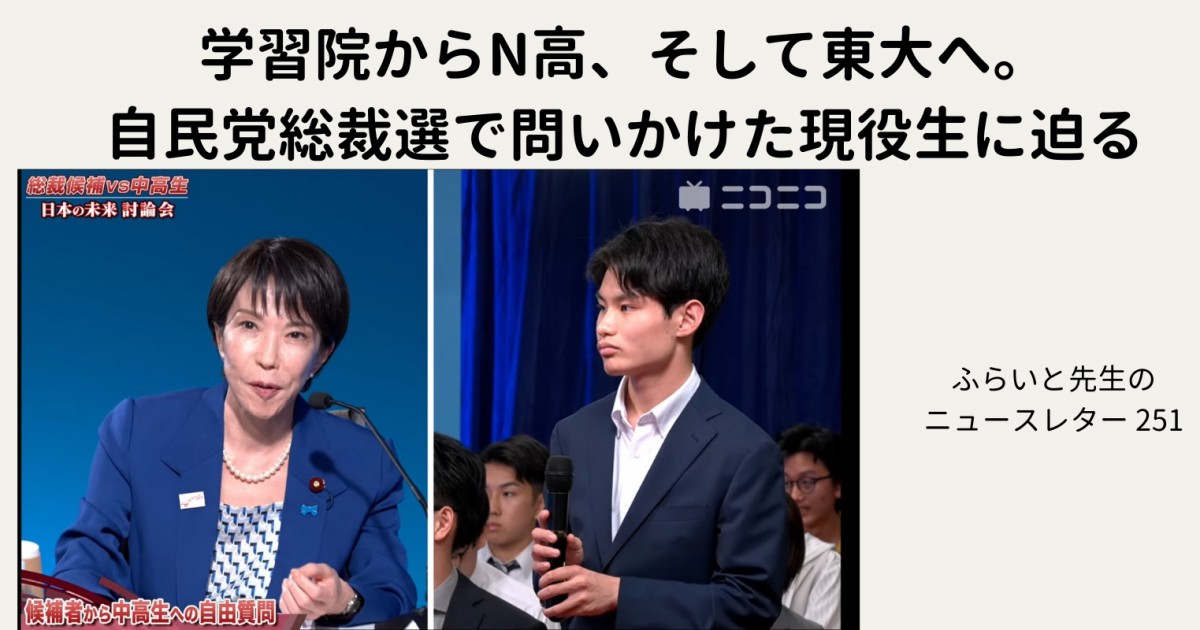男性が父性を目覚めるのに必要なもの
皆様、こんにちは。今月4本目ですね。
今日本から米国に帰る飛行機の中でこれを書いています。
久しぶりの日本といっても半年ぶりでしたが、前回は学会等の準備で忙しくしかも1週間の滞在だったのでゆっくりもできずでした。今回は20日間滞在して、日本での仕事や用事をこなしてきました。
そして、やはり久しぶりの日本は最高でした。帰った翌朝の吉野家の「納豆定食」420円、約2.5ドル!こんな定食を米国で食べようものなら15ドル(2300円)は取られます。日本は色々安すぎますね。物価も上がってきてますが、賃金もそれ以上に上がって欲しい。そんな気持ちで日本を後にしました。
ふらいと先生のニュースレターは、子育て中の方が必要な「エビデンスに基づく子どもを守るための知識」をわかりやすくお届けしています。過去記事や毎月すべてのレターを受け取るにはサポートメンバーをご検討ください。
「父性」はいつ芽生える? ワンオペで気づいた「9カ月遅れの同期」
今回は単発ですが、朝日新聞さんとコラボして朝日新聞(デジタル版)の記事にちなんで、私が記事を書くというトライアルを行ってみます。朝日新聞さんは社会や育児などの記事も多数あり、見応えがある記事が多くあります。
11月25日17:00まで、「デジタル版30周年キャンペーン」を実施中で、初めて登録される方は最初の2ヶ月は無料で使えます。途中解約もできます。なので、一度下のリンクから登録してみて下さい。おすすめです。
さて、今回はこの「父性」はいつ芽生える? ワンオペで気づいた「9カ月遅れの同期」という記事を題材に書こうと思います。
父性はなぜ語られにくい?
実は自分も「父性」というか、父親になった自覚が出たのは非常に遅かったです。
すでに新生児科医という仕事をしてきて毎日数人の赤ちゃんを仕事で見る中で、妻が出産して目の前に長女が出てきた時に、嬉しかった反面、最初に思ったのが
「この子は本当に自分の子どもなのか?」という事でした。
別に疑ってたわけではなくて、妻のお腹にいた赤ちゃんが目の前に急に現れて、「我が子誕生!」という実感がなかったのです。もちろん今では3姉妹ともにかけがえのない存在ですが、あの当時なんだか実感がありませんでした。
それにしても、母性はよく聞く言葉ですが、父性というのは、若い頃には男性達の中で話題になる事はほとんどありません。
日本では「おなかを痛めて産んだ母親だからこそ」という言葉が象徴するように、子どもへの深い愛情やケアは長く「母性」と結びつけて語られてきたという歴史があります。
その一方で、父親の役割はかつて「家計を支える人」あるいは「育児を手伝う人」として扱われ、「父性」がどのように芽生え、子どもや家族にどの程度インパクトを持つのかについて、科学的知見に基づいて語られる事はほとんどありません。
しかし、ここ20〜30年の発達心理学の分野では、父親の関わりが子どもの認知発達、情緒の安定、問題行動の予防にとって重要な役割を果たすことを示す研究が増えてきました。
例えば、父親の養育参加と子どもの発達を追跡した研究をまとめたシステマティックレビュー(複数の研究をまとめて吟味する研究手法)では、父親が積極的に育児に関わる家庭の子どもほど、学業成績が良好で、不安やうつ、非行などの問題が少ないことが報告されています(#1)
また、父親の関わり方も科学的知見が生まれました。
父親が感受性の高い温かいかかわりを我が子にすると、その子どもの認知能力や社会情緒的な適応が良くなり、その大きさは母親の場合とほぼ同程度であることが示されました(#2)つまり、父親も我が子に愛情を持って温かな関わりを行えば、母親と変わらない影響を与える事ができるというのです。
また興味深い研究で、父親の脳に着目した神経科学の研究もあります。
それは、子どもの主たる養育者となった父親の脳では報酬系や共感に関わるネットワークの活動増加を示し、もともと「母性脳」と呼ばれてきた回路に近い形に変化することが報告されたです(#3)
育児をしていると、男性の脳の構造自体が変わってくるというのは興味深いですね。
すなわち、「父性」は、性別といった生物学的な出来事だけから自然に湧き上がる性質なのではなく、育児によって変化し生成されるものなのです。
母性は出産の痛みで芽生える、は本当か?
では少し母性の話もしましょう。
記事中では、パートナーが無痛分娩を選んだという男性に、「出産の痛みが『母性の芽生え』につながるといった言説」についての考えを聞いています。そもそも「母性は出産の痛みで芽生える」というのは本当でしょうか?
いまだに「おなかを痛めて産んでこそ母性が芽生える」というフレーズは、年配の方から医療現場でも聞く事があります。しかも、母親(あるいは今から母親になる女性)が同性である女性から、このフレーズを言われる事もあり、日本ではいまも根強く語られている事があります。
東京都の無痛分娩助成が報じられた際にも、「痛みを軽くして本当に母親になれるのか」といった声がメディアやSNSに散見されました。
私がポストした内容にも以下のような反応があり、いかに世の母親達が世代を超えてこの苦しみを味わっているかと思うと胸が苦しくなります。

助成金出ることで、これからの世代にとって無痛分娩が当たり前の選択になれば良い
しかし、医学研究のデータを丁寧に見ていくと、「強い痛み=良い母性」「痛みを軽くすると母子の絆が弱くなる」という素朴な図式は、少なくともエビデンスとしては支持されていません。
むしろ、過度な痛みやトラウマ的な出産体験が、産後うつにつながりかねない、母子の愛着形成を妨げうるという指摘が増えています。
たとえば中国の前向きコホート研究では、硬膜外麻酔による分娩鎮痛を利用した人は、利用しなかった人と比べて6週後の産後うつのリスクが有意に低かったと報告されています(#4)
その後実施された系統的レビューやメタアナリシスでも、硬膜外などの神経軸性鎮痛は産後うつのリスクを「上げる」というより、全体としては「変えないか、むしろ下げている可能性がある」という方向の結果が多く(#5,6)、少なくとも「麻酔をしたから母性が育たない」というデータは示されていません。
逆に、「痛み」こそが母子のその後の愛着形成に支障をきたすという研究もあります(#7)
分娩時・産後の痛みが十分にコントロールされず、「命の危険を感じた」「誰にも支えてもらえなかった」といったトラウマティックな出産体験をした場合、その後の産後うつや産後PTSDが増え、結果として赤ちゃんへの関わりが難しくなり、母子の結びつきが損なわれたというものです。
ここからは個人的な私見になりますが、母子の絆に影響するのは、痛みそのものというより、「どれだけコントロール感があり、尊重され、支えられた出産だったか」という体験の質であり、適切な鎮痛はその体験を守るための一つの道具にすぎないと思います。
すなわち、「痛みを経験する」ことは母子愛着に良い影響を及ぼさないどころか、悪い影響にもなりかねないのです。
ここで注意ですが、これは別に無痛分娩をしなかった経産婦を非難する意図ではありません。
あくまでも、産む人が自分に合った方法で痛みをコントロールできて、安心して赤ちゃんを迎えられる環境を整えることこそが、その後の育児に向き合う力を育てると言っても過言ではないでしょう。
父性vs母性でなく「育児性」
では、父性はどのように生まれてくるのでしょうか?
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績