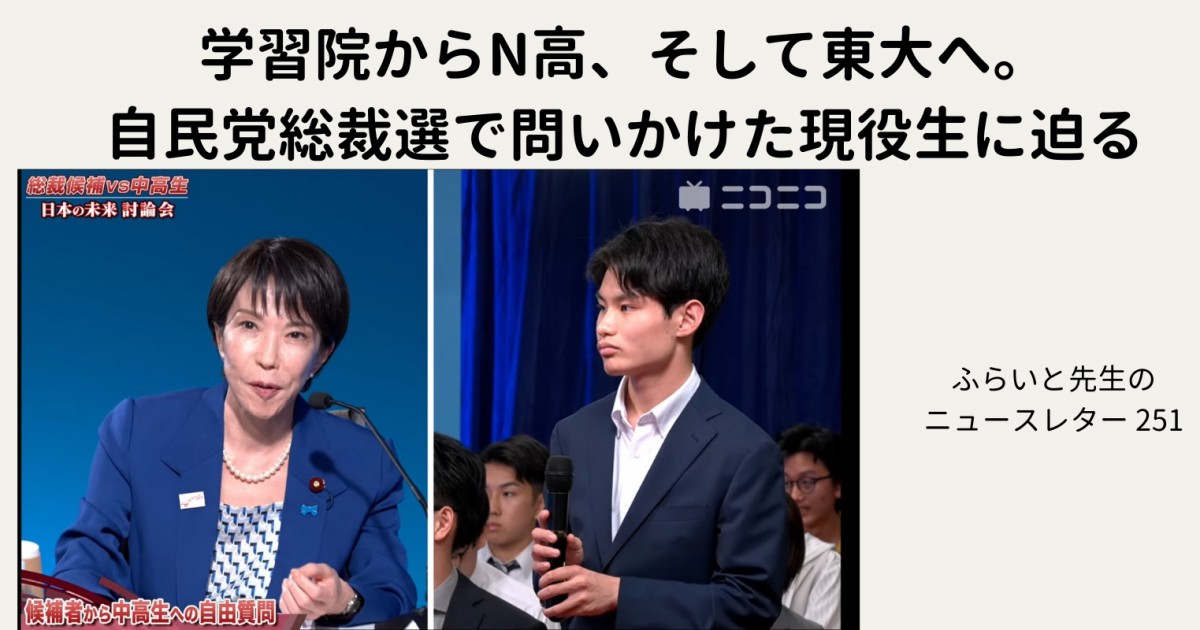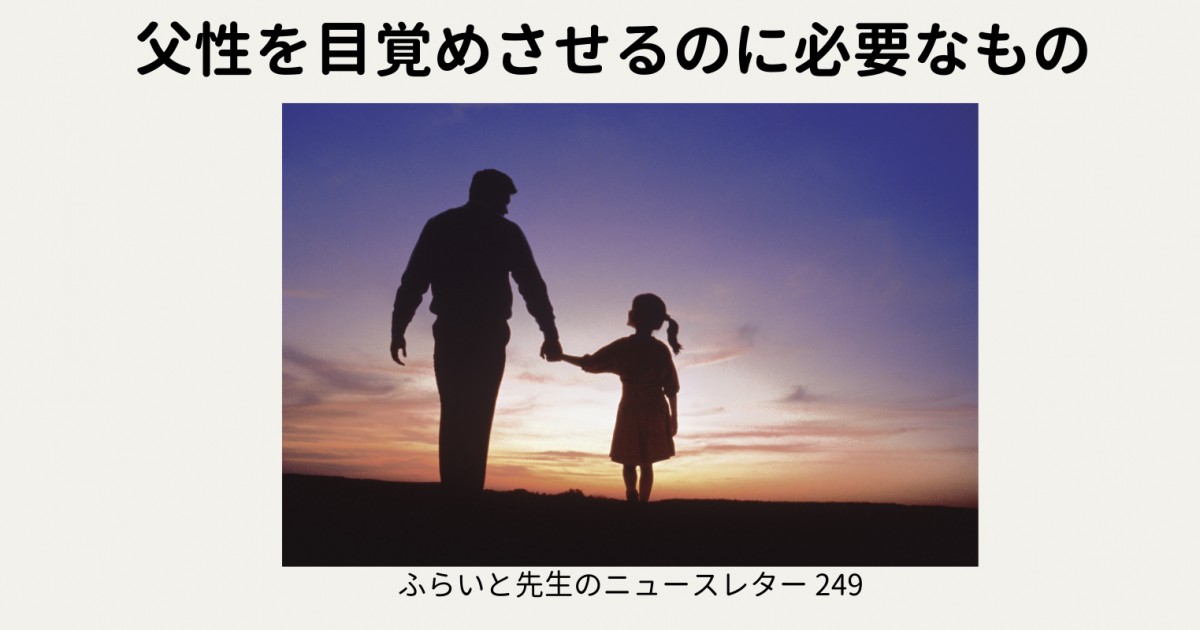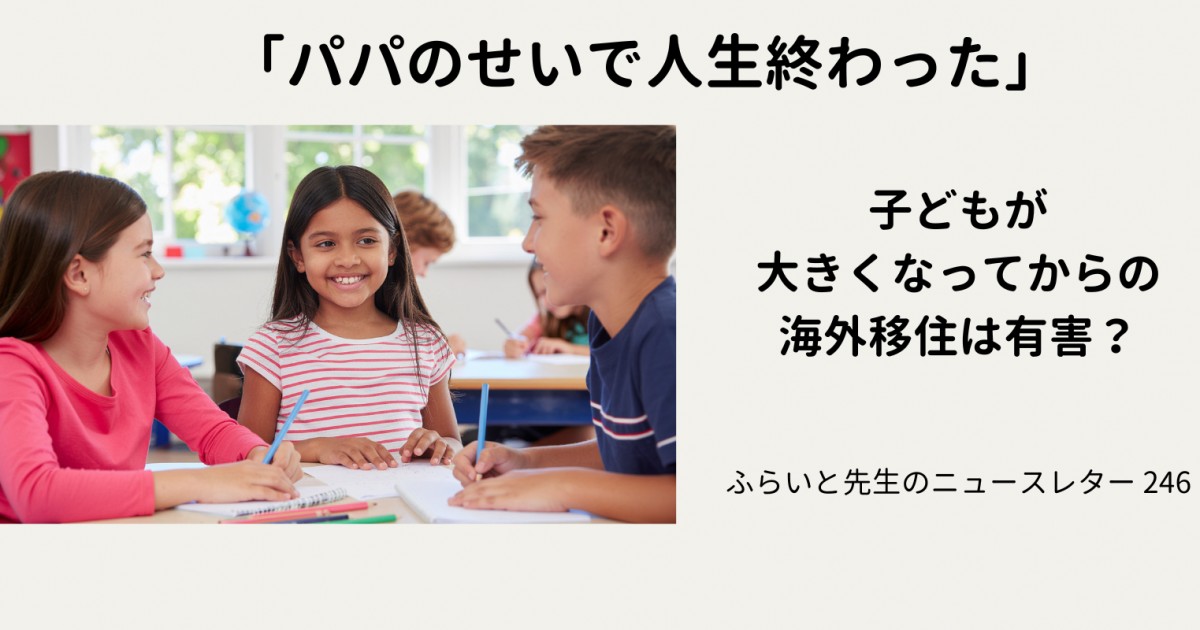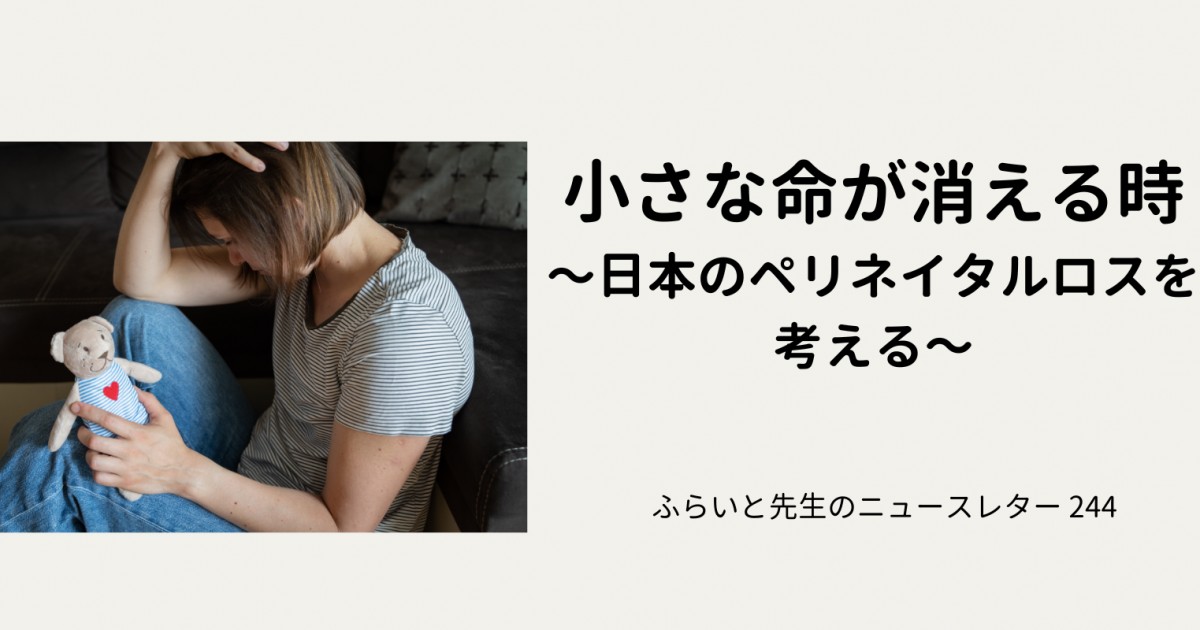子どもが他の子に暴力を振るう「かんしゃく」をどうするか?
さて7月になりました。
7月2本目です。
Q&Aコーナーで様々な質問を頂いているので、順々に返していきたいと思います。
今回の話は「かんしゃく」ですね。子どものかんしゃくに悩んでいる親御さんは結構多いので、そのあたりの話もまとめてみましょう。
ふらいと先生のニュースレターは、子育て中の方が必要な「エビデンスに基づく子どもを守るための知識」を、小児科医のふらいとがわかりやすくお届けしています。
過去記事や毎月すべての「エビデンスに基づいた子どもを守るための知識」を受け取るには有料コースをご検討ください。今回の記事も登録いただければ最後まで読めます。
今回は我が子の「かんしゃく」に悩まれるお母さんからご質問を頂きました。
2歳の保育園に通う子どもがいます。嫌なことがあると叩く、蹴る、噛むことがあります。例えばスーパーに自転車で入ろうとして親が止めると叩いてくる。落ちたゴミで遊んでいて、汚れるから良くないと伝え捨てさせると噛もうとする。保育園の1歳児クラスのよちよち歩きの子を手で押すなど。療育に通うと言う選択肢もちらつきましたが、保育士曰く、過去にはもっと凄い子もいたとコメントももらえました。だからといって上記の行為を見過ごすわけにはいきません。最初は親の気を引きたいのかと思って、叩かれても無視していましたが、特に何の変化もなく。次に叩かれたら痛いよと怒った顔で伝えるようにしましたが、「〇〇君も痛い」と他人の叩かれた痛みを自分が痛かったことに変換してしまいます。少しずつ力もついてきて、本気で叩かれるとすごく痛いので、余裕のない時には怒鳴り声で叱ってしまうこともあります。なにか、他害行為を抑制する適切な対応が研究されているのか知りたいです。
ご質問ありがとうございます。
子どもの「かんしゃく」行動は育児をしていて困りますよね。
特に公共の場でかんしゃくを起こされると、親としてはまいりますよね。我が家は3姉妹とも性格はおとなしい方ですが、何か嫌なことをしなければいけない時はシクシク悲しく泣くタイプです。
先日も5歳の三女が歯医者に虫歯を治しに行ったのですが、このニュースレターでも紹介した目にglitterが入ってしまった件以降、お医者さんにかかるのが嫌いになってしまい、診察室に入るなりシクシク泣いてしまいました。
結局、口を断固として開けないのでとても困りました。歯医者さんも「これはお手上げだ」と米国人がよくする両手をあげるジェスチャーで診療を断られてしまいました。
うちの娘達は泣いてパニックになった時、人を攻撃することはありませんが、実際の小児科で診療をしていると採血や点滴を取る時に「かんしゃく」を起こし、噛みつかれたり、ブーとツバを吐きかけられたりするので、一定数そういう子がいることは理解できます。
よく悩む親御さんに「子どものかんしゃくは我慢するしかない」と声をかける支援者もいますが、親の立場でこれを言われると八方塞がりになってしまいます。
これまでしてきた対応がうまくいかず、お子さんの行動がエスカレートしているように感じると、途方に暮れてしまうこともあるでしょう。子どもの成長過程でよく見られるものですが、親御さんにとっては大きなストレスとなることも事実と言えます。
今回は、海外で行われた最新の研究結果に基づき、2歳のお子さんの他害行為を抑制するための効果的な対応策について、小児科医の視点から分かりやすく解説していきます。
2歳児の攻撃的行動:それは成長のサイン?
まず前提条件として、2歳のお子さんが示す「かんしゃく」は、多くの親御さんが経験する一般的な子どもの発達段階の一部です。
この時期の子どもは、まだ言葉で自分の感情や要求をうまく表現できないため、フラストレーションや怒りを身体的な行動で示すことがあります。
カナダで行われた複数の縦断研究を含むレビューでは、かんしゃくの頻度は生後30か月頃(2歳半)に増加し、その後、就学期にかけて徐々に減少していくことが報告されています(#1)。5歳以上の子供がかんしゃくをくりかえすのは珍しいことです。
これは、お子さんが成長するにつれて感情をコントロールする能力や、言葉でコミュニケーションをとる能力が発達するためです。
特に言葉の発達で言うと、一般的に男の子は女の子に比べてコミュニケーション能力の発達が遅いです。最終的には男女同じになっていくのですが、この言葉が出始める時期は特にその差が大きいと言えます。
かんしゃくは乳幼児期に非常に一般的であり、アメリカ国立生物工学情報センター(NCBI)の出している他の文献でも、2歳児の20%、3歳児の18%が1日に1回以上かんしゃくを起こすというデータもあります(#2)。かんしゃく中の行動として、泣き叫ぶ、体を投げ出す、叩く、物を投げる、噛むといった行動が含まれることも一般的です。
かんしゃくの多くが正常な発達の一部なのですが、一方で全てのかんしゃくが「発達の正常な範囲」であるわけではありません。
#2の文献によれば、かんしゃく中の行動が「自分や他人に身体的な危害を加える」「物を破壊する」といった場合、それは非典型的であり、専門家への相談を検討すべきサインであると指摘されています。
お子さんが「痛い」と言われたことに対して「〇〇君も痛い」と返す状況は、まだ他の人たちの感情を理解し、共感する能力が未熟であるためと考えられますが、このような行動が続く場合は、共感性の発達に課題がある可能性も示唆しており、注意深く見守る必要があります。
海外の研究から学ぶ「やってはいけない」親の対応
親御さんがお子さんの攻撃的な行動に直面した際、つい感情的に怒鳴ってしまったり、無視したりすることがあるかもしれません。子どもが泣き叫ぶとイヤな気持ちになるのは仕方ありません。
しかし、海外の複数の研究は、親のある対応が子どもの攻撃性を悪化させる可能性があることを示唆しています。その親のある対応とは何でしょうか?
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績