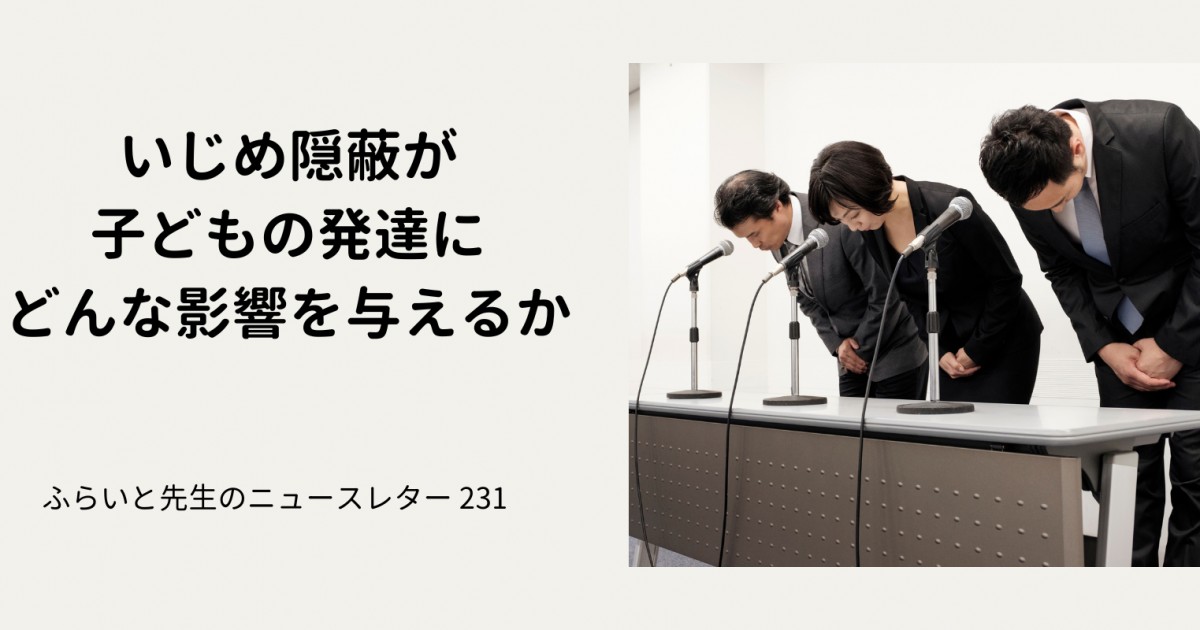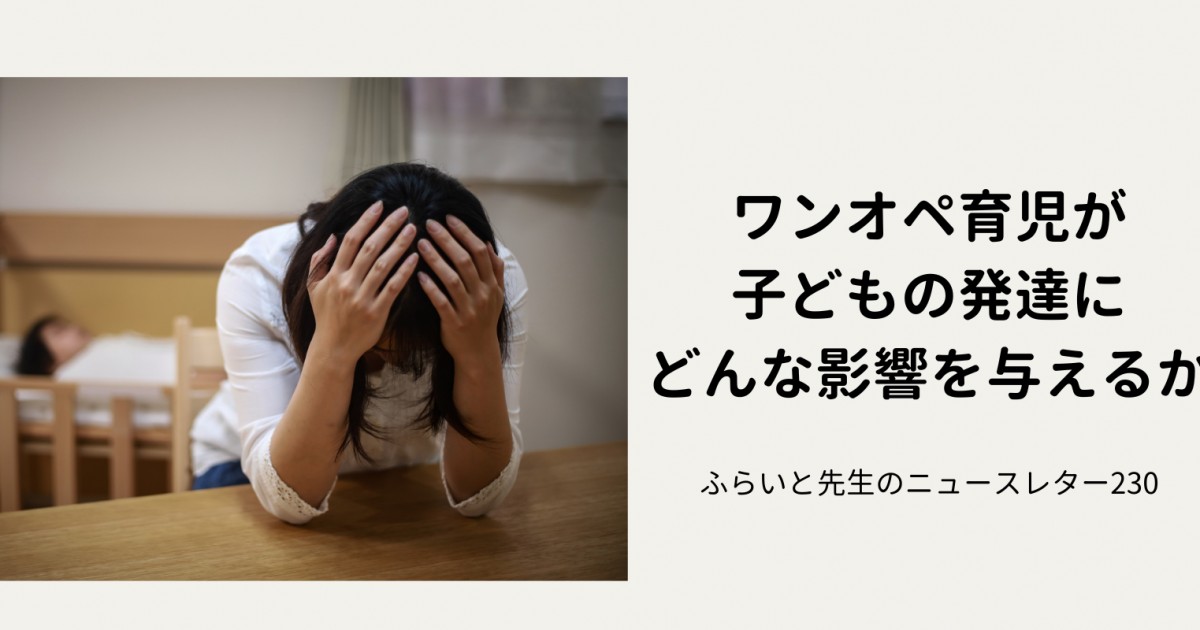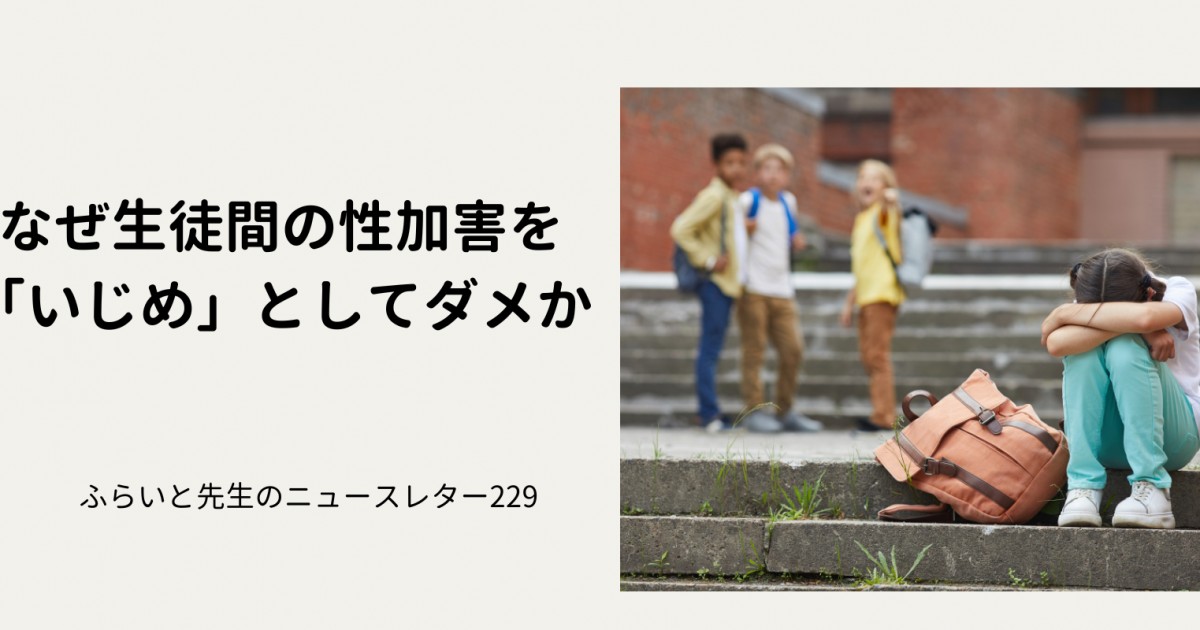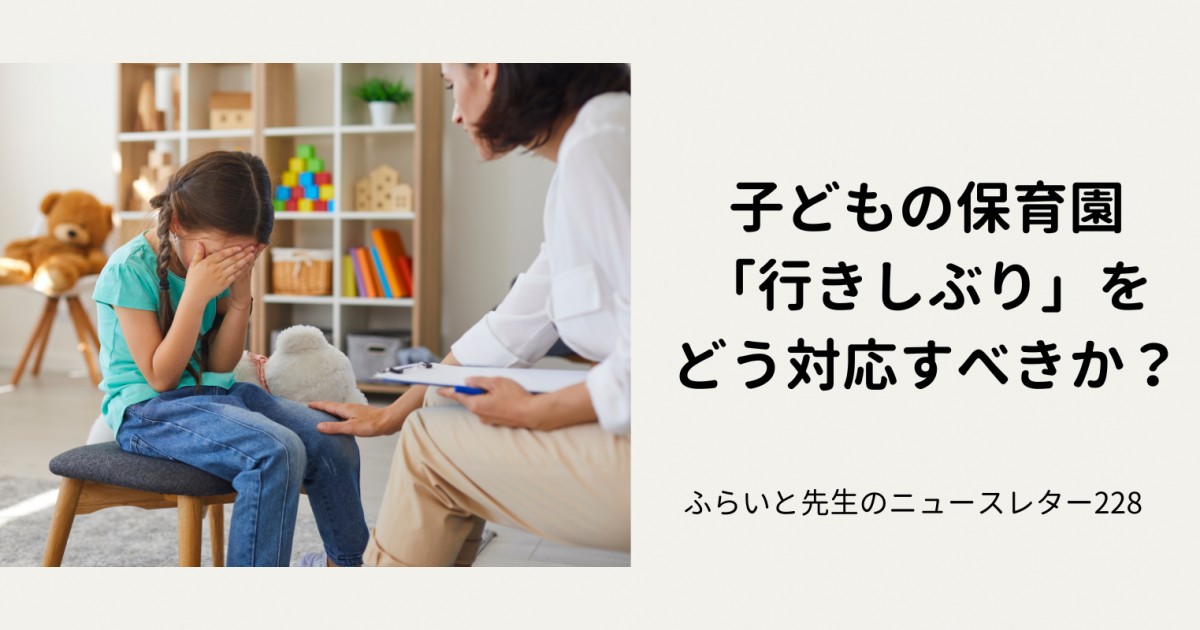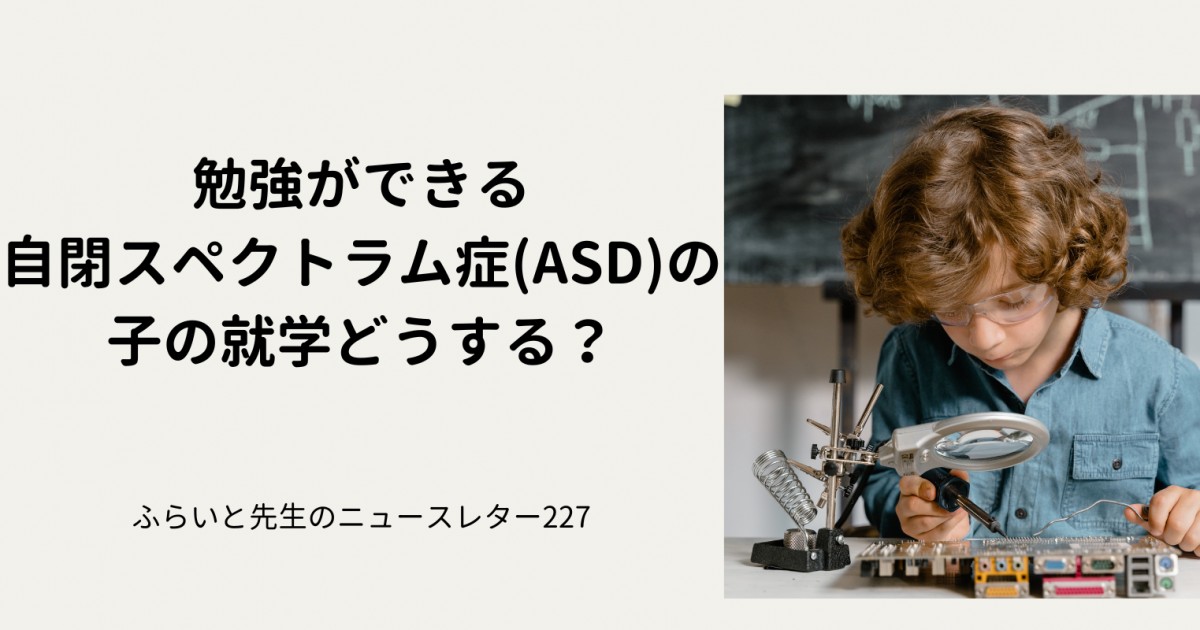小さい頃に病気をしたら、子どもの性格は変化する?
皆さんこんにちは。
皆さんは夏休みをどうお過ごしでしょうか?
米国では6月10日に夏休みに入ってから約2ヶ月半、今週やっと学校が再開されます。本当に長いです。。親としてはようやくといった感じですが、色んな事をできて充実していました。
今回は定期的に頂いているご質問にお答えする回です。
ふらいと先生のニュースレターは、子育て中の方が必要な「エビデンスに基づく子どもを守るための知識」を、小児科医のふらいとがわかりやすくお届けしています。
過去記事や毎月すべての「エビデンスに基づいた子どもを守るための知識」を受け取るにはサポートメンバーをご検討ください。今回の記事も登録いただければ最後まで読めます。
いつも有益な情報をありがとうございます。毎回配信を楽しみにしております。男子2人の子育て中です。長男は出生時に重症新生児仮死で産まれ、数日NICUで診ていただきました。出産した病院の皆さまのお陰でその後は発達等問題なく、フォローも1歳前に卒業し今は元気な小学生です。決して穏やかな性格ではないですが、保育園の頃から年齢の割に落ち着き、周りを見て達観しているような感じを受けます。NICUに行くほどの経験がそうさせているのでは?と感じることもあります。一方で次男は問題なく産まれ、「ザ次男」という感じでやや拗らせ気味の自由奔放な性格です。そこで気になったのは、小さな頃に病気や入院など大きなイベントを経験している子は精神的な発達が変化する、など検討された研究などありますでしょうか。また逆に、子の入院などを経験した保護者の子への接し方の変化もあるのかもしれない、と思いました。私自身、出産の時の気持ちを考えると多少のけがなどに対しては死ななければ大丈夫、くらいの気持ちでどっしりと構えて生活しています。この点についても何か知見があるのか、先生のご経験などもふまえてお伺いできたらとてもありがたく思います。よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。
長男くん、それは大変な思いをされましたね。きっと親御さんも当時心配されたことでしょう。
どれだけ妊娠経過が順調でも、産まれるその日まで油断できないのがこの新生児仮死というものですよね。私も長女、次女、三女と分娩立ち会いをしまして新生児科医として経験はたくさん積んだはずですが、背筋が凍る分娩を多数見てきたおかげで三女の分娩立ち会いが1番緊張しました。
知るという事は逆に恐怖心が増大する事もあるのだなと感じました。
私も新生児医療現場で長年多くの赤ちゃんを診療してきましたので当然、重症新生児仮死も多く診療してきました。急性期に親御さんから1番多い質問は圧倒的に
「この子は障害が残りますか?」です。
発達を見ていく中でしか判断できませんし、急性期では当然ながら判断できない事が多いので、100%「わかりません」とお答えするのですが。
そして重症新生児仮死で治療をしてNICUを退院する赤ちゃんは、発達外来で6歳まで診療していきます。その際に1番多い質問は「将来どのように発達していくのか」です。
今回の質問内容は小児科医として、また一人の親として、お母さんの深い洞察力と愛情に感銘を受けました。長男くんが見せる年齢を超えた落ち着きや達観した様子、そしてお母さんご自身が感じている「死ななければ大丈夫」というどっしりとした強さ、素晴らしいと思いました。
ただ意外と、発達外来で性格に関する質問はされた事がありませんでした。なので色々と調べてみたいと思います。
お母さんが抱いている二つの大きな問いに、海外の研究成果を交えながらお答えしていきます。一つ目は、「NICU(新生児集中治療室)に入るほどの大きな出来事を経験したお子さんの精神的な発達は、どのように形作られていくのか」。二つ目は、「お子さんの入院という危機的な状況を乗り越えた親の心や子育てへの姿勢は、どのように変化するのか」
順番に解説していきたいと思います。
NICUでの早期ストレス
新生児仮死という生命の危機に瀕し、NICUで過ごした経験は、単なる病気の記録ではなく、お子さんの心と脳が世界を学ぶ最初の「原体験」となります。
この経験を、「早期ストレス」という概念で捉える考え方があります。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績