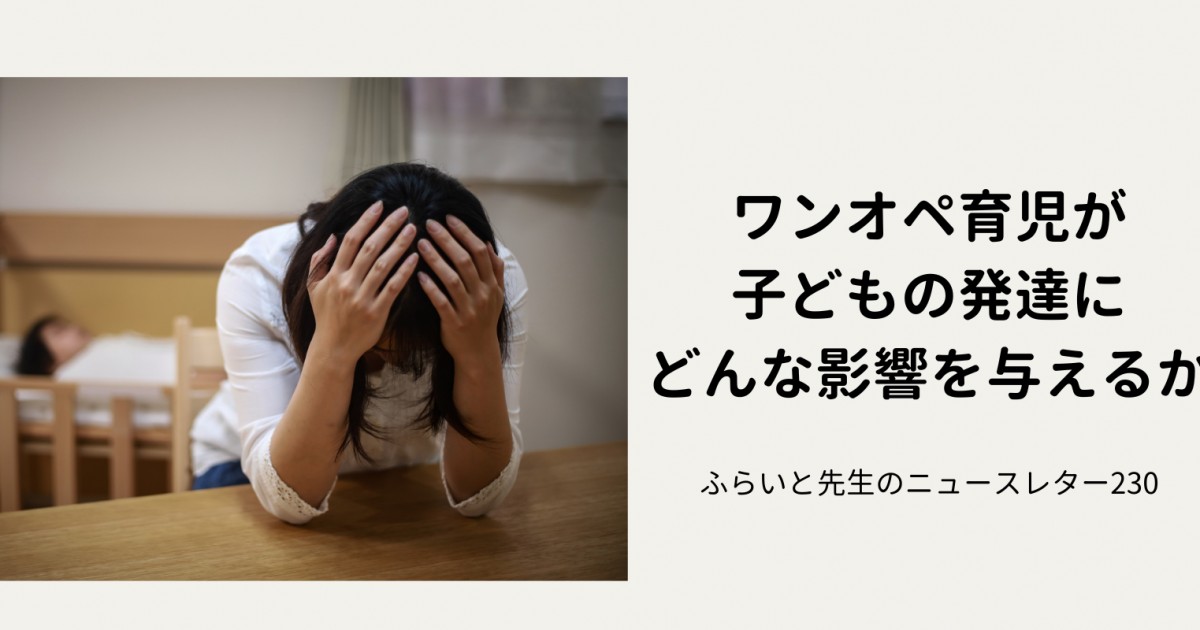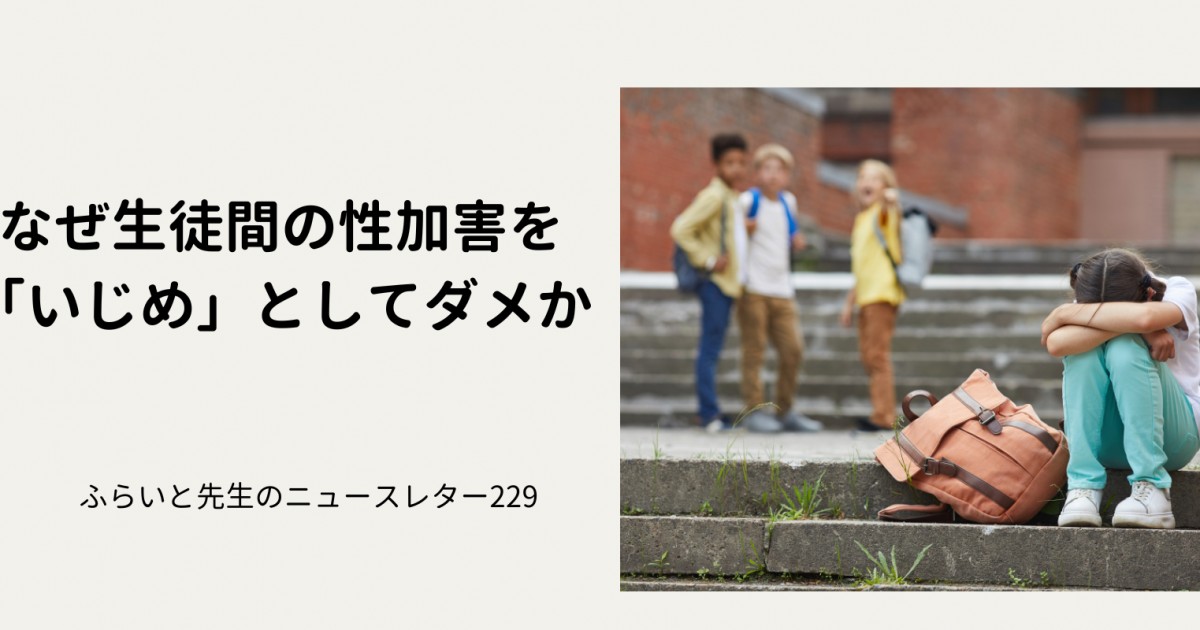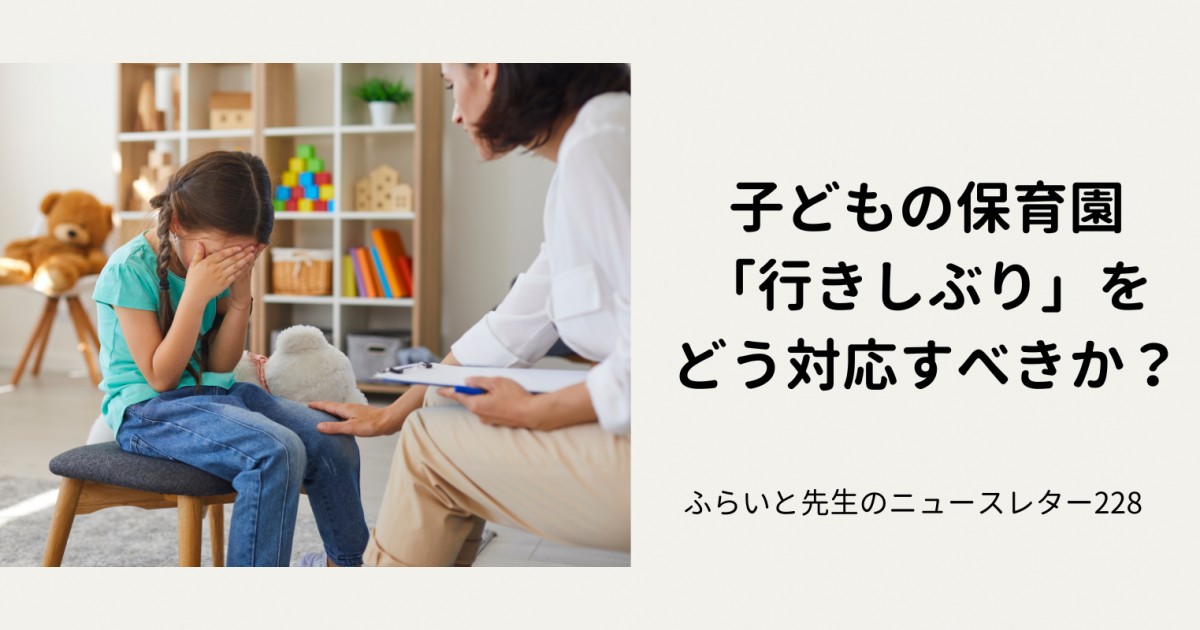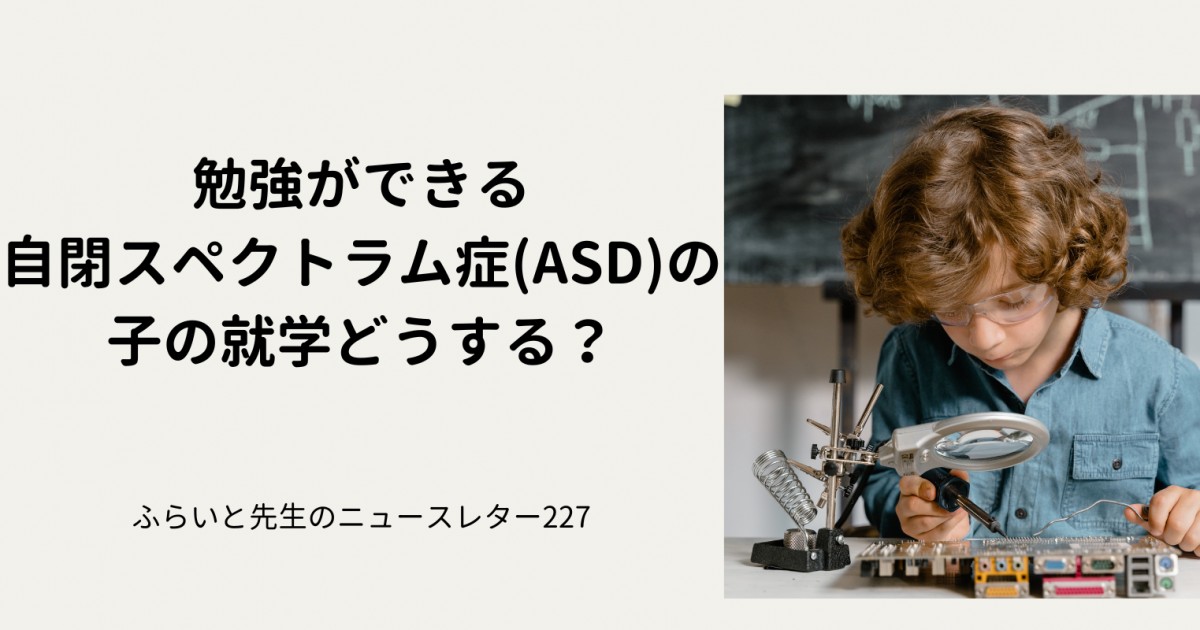いじめ隠蔽が子どもの発達にどんな影響を与えるか
皆さんこんにちは。
8月も中旬となりお盆の季節ですね。そろそろ暑さが落ち着いてくる頃でしょうか。
さて今回は先週話題で持ちきりだったいじめ隠蔽疑いの件を考えます。
ふらいと先生のニュースレターは、子育て中の方が必要な「エビデンスに基づく子どもを守るための知識」を、小児科医のふらいとがわかりやすくお届けしています。
過去記事や毎月すべての「エビデンスに基づいた子どもを守るための知識」を受け取るには有料コースをご検討ください。今回の記事も登録いただければ最後まで読めます。
既にニュースでご存知の方も多いと思いますが、今夏の甲子園に出場中のある高校が大会を途中で辞退することになりました。
それは広島県代表の広陵高校です。
いじめの被害生徒の保護者のものと見られるSNSアカウントが、7月23日にとある高校内で起きた暴力事件に関して突如発信を始めました。
それは今年の1月から集団暴行事件を事細かく「告発」する内容でした。
他の報道によれば、高校側は8月5日、硬式野球がこの暴力事件に関して日本高校野球連盟、通称「高野連」から厳重注意を受けていることを明かしました。今年1月に「部員間の暴力を伴う不適切な行動」が起きており、日本高野連から3月5日の審議委員会を経て厳重注意処分を受けていたのです。同校の報告書によると加害生徒は4人で、「胸を叩く、頬を叩く、腹部を押す、胸ぐらをつかむ行為」をしたそうで、SNSで告発された加害者と人数も暴力の内容も違うが被害生徒は3月末に転校している事が明らかになりました。
このアカウントの発信内容と報道内容が一部一致した事から、大方の人達はこの告発は広陵高校のものだと同定されたのです。
しかし、この暴力事件はいじめ防止対策推進法で定められる「いじめ」に相当し本来は広島県に報告義務があるにも関わらず、学校側はそれをしていなかった事が追加で報道されました。
これにはSNSの民達からは疑問の声が上がっていました。
「完全にいじめ隠蔽ではないか」
「高校は完全にOUT」
「この問題の影響はこの高校だけでなく、高野連やメディアにも広がるだろう」
その声は様々で、中には広陵高校を擁護する声も上がっています。
「すでに学校側も調査して高野連からは厳重注意という処分が下されている。SNSの時代にその時点で公表しておかないから、こんなことになるのだが、これは終わった話で、大会が始まってから、いまさらぶりかえして、とやかく言うのはおかしな話」と野球界の大御所は述べていますが、これに関してはどうなのでしょうか?
全く関係のない自分がSNSでの動向を見ていても、この暴行事件に関してSNSで言われている事のどこまでが本当でどこまでが虚偽なのか検討もつきません。
また現在の情報は主にSNSやメディア上の内容に基づいており、公式な調査結果や刑事処分が確認されていないため、事実関係には慎重な判断が必要なのは注意が必要です。そのため、いじめの隠蔽があったのか、その真偽ははっきり分かりません。
なので、ここから一般的な話をします。
深刻ないじめが社会的に発覚した時に、よく話題に上がるのは「学校はいじめはなぜ隠すのか」と呼ばれるものです。
今回は「一般的な話として」学校をはじめ周りの大人がいじめを隠すことは、成長過程中の子どもの成長や発達にどのような影響を与えるのか検証していきたいと思います。
いじめは単なる通過儀礼ではない
注:「いじめ」という言葉は、学校内での暴力事件をまるで犯罪ではないような印象を与えるので個人的には好きではないのですが、この記事では便宜上「いじめ」と呼ぶことにします。
「いじめ」は、小児科医として子どもの健康と成長に寄り添う中で深刻な事態を引き起こします。
また、今なお一部で囁かれる「いじめは成長過程の通過儀礼だ」という考えは、極めて危険な誤解です。この言葉は、被害を受けている子どもの苦しみを矮小化し、本来であれば社会全体で取り組むべき深刻な問題を個人の問題へとすり替えてしまいます。
いじめは、単なる子ども同士の「ケンカ」や「からかい」とは本質的に異なります。その定義には、国際的に共通する三つの重要な要素が含まれています。
第一に「意図的な加害行為」であること、第二にその行為が「繰り返し」行われること、そして第三に被害者と加害者の間に「力関係の不均衡」が存在することです 。この力関係の不均衡こそが、いじめの最も悪質な点です(#1)
被害を受けた子どもは、自力でその状況から抜け出すことが極めて困難な状態に置かれます。いじめの形態は、殴る蹴るといった直接的な身体的いじめ、悪口や脅しなどの言語的いじめだけでなく、仲間外れや無視、悪い噂を流すといった、目に見えにくい関係性のいじめ、そして近年深刻化しているインターネットやSNSを介したサイバーいじめなど、多岐にわたります。
このいじめの問題は、特定の国や地域に限った話ではありません。
世界中の子どもたちの約3人に1人が、人生のある時点でいじめを経験したと報告しており、そのうち10%から14%は6ヶ月以上続く慢性的な被害に苦しんでいます(#1) これは、いじめが普遍的な社会問題であることを示す何よりの証拠です。
ではまず「いじめ」自身は、子どもの発達にどのような影響を与えるのでしょうか?
いじめがもたらす最も顕著な影響は、精神的な健康問題です。特にうつ病との関連は、多くの研究で一貫して示されています。
2023年に医学雑誌『BMC Psychiatry』に掲載された複数の研究を統合的に分析した研究結果(#2)では、いじめられた経験のある子どもは、そうでない子どもに比べてうつ病を発症するリスクが2.77倍も高いことが明らかになりました。
さらにこの研究では、興味深いことに、いじめをした事がありいじめられた経験もある「bully-victim」と呼ばれる子どもたちが最もリスクが高く、非関与者に比べてうつ病リスクが3.19倍にも上ることを示しています。
いじめられる子が1番リスクが高いと思いきや、どちらも経験した側の方がリスクが高いとは意外な結果ですね。いずれにせよ、いじめに関わる事は子どもの成長と発達に悪影響を与えることは間違いなさそうです。
また影響はうつ病だけにとどまりません。
不安障害もまたいじめと強く関連しています。全般性不安障害、社交不安障害、パニック障害、さらには強迫性障害といった様々な不安症状のリスクが高まることが指摘されています。特に深刻なのは、いじめが妄想的な思考や認知の混乱といった精神病様症状にまでつながる可能性があるという点です。
ここに興味深い研究があります。英国で11,108人の双子を対象に行われたJAMA Psychiatryの研究です(#3)
双子研究の最大の強みは、遺伝情報が100%同一である一卵性双生児のペアを比較できる点にあります。もし、一卵性の双子のうち、片方だけがいじめられ、もう片方がいじめられていない場合、その後に生じる二人の精神状態の違いは、遺伝や共有された家庭環境ではなく、いじめという経験そのものによって引き起こされたと強く推測できるのです。
分析の結果、いじめ被害は、不安、うつ、多動性・衝動性、不注意といった問題の直接的な原因となることが示されました。特に不安への影響は少なくとも2年間持続し、妄想的な思考への影響は5年後まで続くことが確認されたのです。
このようにいじめが子ども達の健康に「長期間」影響を与える事は明白であり、「単なる通過儀礼だから気にするな」という認識では困るのです。
いじめの「助けて」が届かない学校の隠蔽
いじめそのものが子どもに与えるダメージは計り知れませんが、そのダメージをさらに増幅させ、より深刻で長期的な心の傷へと変えてしまう、もう一つの要因に焦点を当てます。
それは、いじめが起きていることを知りながら、学校がそれを看過したり、矮小化したり、あるいは組織の評判を守るために積極的に「隠蔽」したりする行為です。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績