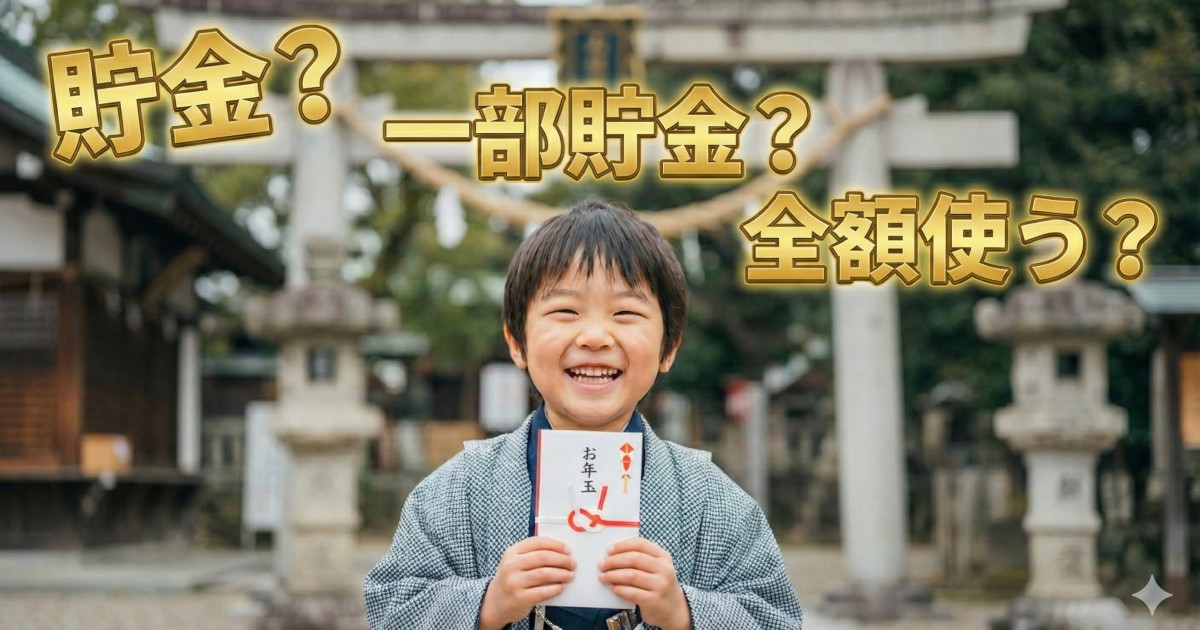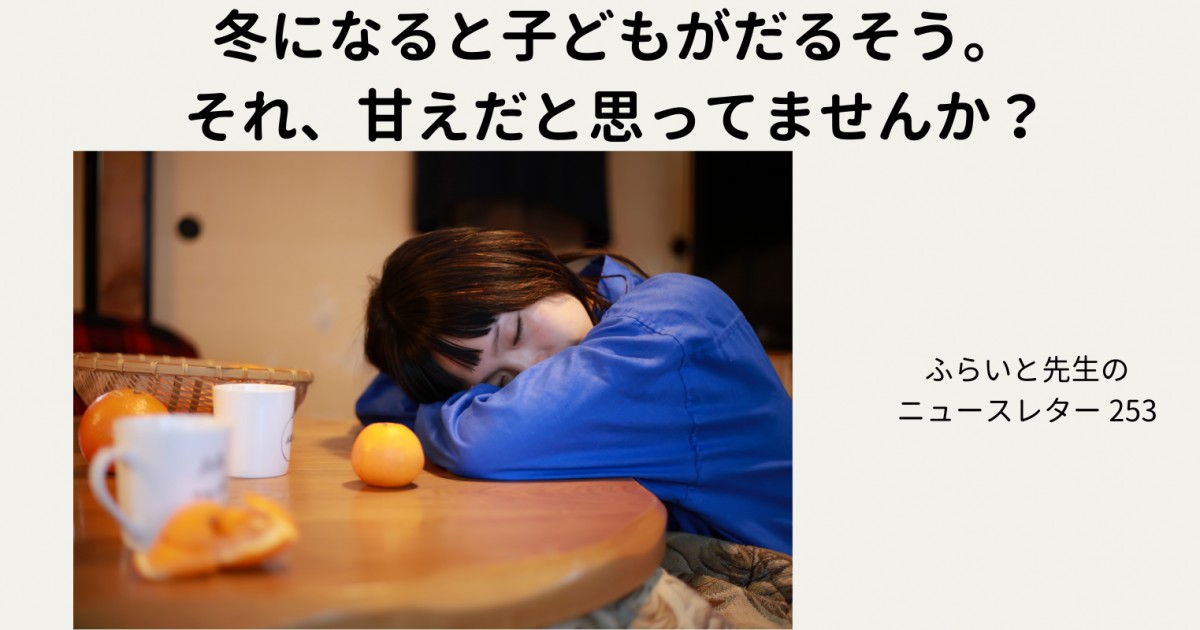山田太郎・参議院議員に聞く、こども政策のこれから
皆様、こんにちは。
5月も多くの方々にこのニュースレターに御登録頂きました。引き続き頑張って書いていこうと思っておりますのでよろしくお願いします。
「子どもは票にならない」と言われて久しいですが、その中でも子ども政策のために尽力してくれる存在は貴重です。一方、逆に医療などの現場にいる人間はその内情を知らない事も多いです。今回は通称こども族と言われる参議院議員の山田太郎議員をゲストにお迎えし、「こども政策のこれから」についてお話を伺いました。
尚、本記事において開示すべき利益相反はございません。
ふらいと先生のニュースレターは、子育て中の方が必要な「エビデンスに基づく子どもを守るための知識」を、小児科医のふらいとがわかりやすくお届けしています。
過去記事や毎月すべての「エビデンスに基づいた子どもを守るための知識」を受け取るには有料コースをご検討ください。今回の記事も登録いただければ最後まで読めます。

山田太郎参議院議員
今回のゲスト、山田太郎議員の詳細なプロフィールはこちらから↓。個人的に習慣や癖に「エゴサーチ」と書いててユニークだと思いました。
今までの自殺対策は子ども抜きだった
今西「本日はお忙しい中、ありがとうございます。山田太郎先生のことをご存知ない方もいらっしゃると思いますので、まずは自己紹介からお願いできますか?」
山田議員(以下、山田)「参議院議員の山田太郎です。子ども政策に特に力を入れておりまして、こども家庭庁の創設やここども基本法の成立に取り組んできました。本日はよろしくお願いします」
今西「よろしくお願いします。早速ですが、こども族と言われる山田議員が、子ども政策の中で特に大きく取り組んできた事はどのようなものがありますか?」
山田「特に取り組んできた大きな仕事といえばこども家庭庁の創設です。2021年1月24日当時菅総理に対して“こども庁“が必要だということを単独で主張して官邸まで乗り込みました。
2022年6月にこども家庭庁設置法とこども基本法が成立することになりましたが、それまでは政府に子ども政策を総合的に取り組む司令塔がなく、障害児や子どもの自殺対策専門の部署もありませんでした。厚労省や文科省、内閣府がそれぞれ独自に動いていたりと仕組みがバラバラでした」
今西「それは山田議員が子どもの色んな問題があると認識されていたからでしょうか?」
山田「日本は若い人達が自殺でなくなる数が相当多いのです。日本では毎年約500人の子どもが自殺しています。昨年も529名の子どもが命を絶ち、過去最多でした。これは緊急事態ということで、党内に自ら「こどもの自殺対策PT」を設置し、座長をさせて頂いたりと積極的に取り組んでいます」
今西「山田議員といえば子どもの取り組みの他にデジタルの方面でも強いイメージがありますが?」
山田「デジタル庁を創るということもさせて頂き、その後、デジタル大臣政務官として、日本のデジタル政策の中心となる「デジタル重点計画」も責任者としてまとめさせていただきました。そのほか、文部科学大臣政務官としても積極的に子ども政策を一所懸命やらせていただきました」
今西「マルチなご活躍ですね。参議院は6年間という長いようで短い期間だったと思いますが、具体的にはどのような政策を実現されたのでしょうか?」
山田「もっとも力を入れて取り組んできたことは、子どもの命・安全を守るための政策です。今国会で、自殺対策基本法の改正を行い、子どもの自殺について、具体的な対策を法律に盛り込みました。今後は学校や地域での相談体制の充実や、メンタルヘルスの推進も重要だと考えています。
信じられないと思いますが、それまで日本の自殺対策は子どもに特化して議論されたことはなかったのです。これがしっかり法律に明記される事は、非常に大きいと思います」
(注釈;自民党の孤独・孤立対策特命委員会は5月13日、子ども達に第三の居場所を確保するための提言案をまとめた。その中心人物に山田太郎議員の名前がある)
今西「子どもに特化した自殺対策がなされていなかった事は知らなかったです」
山田「それから、教員による不適切な指導が原因となる指導死や、体罰・不適切な指導そのものを撲滅することに取り組んでいます。文部科学省が10年ぶりに生徒指導提要(教員向けの指導マニュアル)を改定する際、不適切指導が子どもを自死に追いやる可能性があることを明記するとともに、不適切指導の具体例や、どのように対応しなければならないのかも示すことになりました。
そして、いじめ対策に関しても、文科省単独の所管から、こども家庭庁も共管として対応すると決めさせたことも、大きな前進です。学校現場や教育委員会だけの閉じた対応ではいじめの問題が解決しない場合も多いんです」
今西「なるほど。法律に抜けがちだった子どもへの対応もしっかり法律内に記述してもらうというのは大切なのですね」
山田「2つ目は、社会的養護の支援拡充です。
社会的養護とは、親の病気や虐待などで親と暮らすことができない子どもを社会で育てることです。日本で社会的養護を必要とする子どもは約4万2千人います。日本では長年、乳児院や児童養護施設での養育が中心でしたが、私自身、乳児院を視察した際に、愛着障害などの問題に直面して衝撃を受けました。
そこで家庭的養育、特に里親制度の推進のため、里親のなり手を増やす政策や里親支援の充実にも取り組んでいます。もちろん里親に預けることが難しいケースもあります。しかし、乳幼児期の養育環境は愛着障害の原因となりやすいですから、特に家庭的養育原則を徹底すべきだと考えています」
今西「愛着障害というのは?」
山田「幼少期に安定した養育関係が築けず、情緒や社会的な発達に影響を及ぼす状態です。乳児院には泣かない赤ちゃんもいます。特に乳児期の安定した養育者の有無は、子どものその後の成長に大きく影響を与えると認識しています」
母子家庭で育った中で感じたこと
今西「次に挙げる政策は何でしょう?」
山田「障害をもつ子の政策です。
具体的な取り組みをひとつあげると、産科医療補償制度の見直しです。分娩中に産道を通る際に重度の脳性麻痺になってしまうお子さんが一定の割合で出てきます。そのお子さん達や家族に補償する産科医療補償制度というのがあるのですが、基準が古かったために重度の脳性麻痺の子どもたち約500名が補償対象から外れてしまっていた問題がありました。そこで、その子どもたちに特例措置で遡及して補償を適用しました」
今西「たくさん取り組まれたのですね。子どもの政策取り組みとして、赤ちゃんから思春期まで幅広くされていて感服するところですが、そもそも山田議員が子ども政策に関わるきっかけは何だったのですか?」
山田「実は私自身が母子家庭で育ったこともあり、子どもの貧困や社会的養護の問題は自分ごととして感じていました。直接的なきっかけは、政治家になってすぐに乳児院や児童養護施設、里親さんの現場などを訪れたことです。
また大学教員として学生と関わる中で、若い人たちの将来不安を解消したいという想いを強くもつようになりました。学生に「趣味はなんですか?」と聞いた時に「お金を貯める事です」と言うんです。今、子ども達は将来不安を感じています。どれだけ頑張っても報われないという根本的な絶望がある気がしています。彼ら若者も生きづらさを感じている。学生たちが感じているそんな社会への不信感を払拭したいというのが原点です」
今西「若い人達が希望を持てる社会というのは大切ですよね。けどこれだけの政策を進めていくのは並大抵のことではないと感じています。子どもの政策を進める上での困難はありましたか?それをどのように乗り越えられたのでしょうか?」
山田「子どもの政策全般を進めていくにあたって、行き詰まったことはとても多かったです。こども家庭庁の設立には、党内でも、子どものことは基本的に家庭で全部するべきものであって、政治や政府が介入するべきじゃないという意見も多くありました。
しかし、子どもを取り巻く家庭の環境は大きく変わっていますし、共働きの時代の中で家庭も余裕がない状態となっています。行政や社会がそういった家庭をしっかりサポートしていく必要がある。そのためには“こども庁”が必要になってくる。それが最初のコンセプトです。粘り強く説得し、世論や地方議員の支援を受けて設立を実現しました。世論形成のためのシンポジウム開催や積極的な情報発信を工夫しました」
「こども家庭庁か」の攻防
今西「なるほど。“こども庁”と言われてましたが、こども家庭庁に“家庭”の文字が入るようになったのはどのような経緯があるのですか?」
山田「一つは2021年の年末に名称問題が起こります。“こども庁”なのか、“こども家庭庁”なのかと。私はこどもをまんなかにした社会を実現するために、あくまでも“こども庁“と主張してきたのですが、家庭の問題も取り入れろと言うことで”こども家庭庁“、なんなら”家庭庁“だと、こういう意見もありました。物事の名称は体を表すということで、私はすごく大事だと思っていて、こだわってきました。しかし、そこは妥協する形で”こども庁“が設立できるのであれば、受け入れざるを得ないと思いました。
その後、さらに困難が訪れました。
こども基本法を与党内で通す時の話です。日本は、国連の「子どもの権利条約」を批准してから30年間近くも国内法の整備を放置していました。子どもの権利を認めようということに関して、「子どもは親の所有物だ」という考え方とどうしてもぶつかりました。
そんな中で、しっかり子どもを権利の主体として彼らの意見を聞いたり彼らにも権利はあるのだと相当議論を交わしてきました。この法律が通ったのは2022年6月末なので、国会会期の閉会日前日でした。ですから、間に合わなかった可能性もありました。途中、菅政権から岸田政権に変わった政権交代がありました。
当初、菅さんに強いリーダーシップで力強く進められていました。政権というのはどうしても、前政権の打ち出した政策を否定したがるっていうところが、まあ本音としてはある。そのため政権交代の時に続かない可能性があった。これについては総裁選で「子ども政策を議論する公開討論会」を仕掛けて、どの候補者が総裁になったとしても、こども家庭庁やこども基本法は作るのだということを認めさせたっていうのは、大きかったと思っています」

自民党総裁戦で行われたこども政策公開討論会。自民党で行われたというかなり画期的な試みだった
子どもの医療と性被害
今西「よくわかりました。話題は変わりますが、小児医療や周産期医療についてはいかがでしょう?私の専門ということがありますが、やはり子どもにとって医療は欠かせないものです」
山田「具体的に地域の医師不足や医療施設の偏在を解消するため、遠隔地から出産施設に通う際の交通費や宿泊費支援を充実させる政策を進めてきました。小児科医や産婦人科医の育成や配置にも力を入れ、地域間格差をなくす施策も推進しています」
今西「素晴らしいですね。コロナ感染流行時にこういった子どもの医療や保健がボロボロになってしまいました」
山田「新型コロナ感染大流行時の対処は所管庁の縦割りで現場は大混乱しました。典型的なケースで私も覚えているのは、厚労省が所管する保育園ではマスクをつけて、文科省の所管する幼稚園はつけないとか、今度は、二歳以上はマスクをつけろと言って、後で撤回をしてみたりとか。とにかく子ども政策の司令塔がなく、バラバラだった事は、コロナ禍での反省点というふうに思ってます」
今西「確かにその通りですね。私も海外に住んでいて客観的に日本を見ることが多くなりましたが、そこで1番課題感が残るのは子どもの性被害問題です。日本でも議論されてきた子どもの性被害防止策についても教えてください。」
山田「性犯罪者から子どもを守る『日本版DBS(犯罪歴確認制度)』を導入して、これが本当のスタートだという風に考えています。2016年1月に国会の質疑でも性虐待の担当部署がないことを政府に対して問題提起したことがあります。犯罪が起きなければ警察でない、学校でなければ文科省ではない。このような縦割りを超えるためにも、こども家庭庁が必要な理由です。
そして当然ですが、いくらDBSを使ったとしても、結局それは性犯罪の前科がある人に子どもと関わる職業に就かせないっていうだけの制度なので、根本的な解決にはなってないです。それは、性犯罪には初犯が多いからです。
包括的性教育や、被害を受けた子どもの継続的ケア体制の構築も重要で、ここは同時並行で早急に進めていく必要があります。特に学校現場での性教育の充実が求められていると思います。
そして、最後に性被害にあってしまった子どものケアが日本は非常に遅れています。そこはアメリカのように司令塔となるチャイルドアドボカシーセンター(CAC)が日本にも必要だというのは、私も2024年にニューヨークで視察をして感じたところであります。子どもの性虐待対策の次のステージとしては、そのケアする部分であったり、子どもたちに対して、事前に性教育等を含めて人権に関する考え方について議論することをこれから展開するべきだと思っています」
(注釈:米国には900箇所以上あるCACは、日本には2箇所しかない。しかもどちらも神奈川県)
今西「教育と医療の連携も重要ですが、その取り組みはいかがでしょうか?また、保育現場の課題も多いですよね。」
山田「医療と教育現場の連携を進めるため、三鷹市など先進的な取り組みを全国に広げる医療教育コーディネーター制度の推進を考えています。医療と教育の間に立つ専門職が必要であると考えています。
保育士の給与に関しては約10%改善しましたが、まだまだ足りないと思っています。賃金だけでなく、デジタル化による業務の改善、促進も進めています。保育士の業務の全体の33%が事務作業、月に63時間も事務に割いているというデータがあります。DXで業務負担の軽減をして、生まれた時間を直接的な保育にあてて、質を向上させていくことを進めています」
今西「なるほどまだまだ取り組む課題は多そうですね。最後にざっくりとした質問で申し訳ないですが、山田議員が理想とする社会像を教えてください」
山田「子ども自身が『社会や周囲から守られている』と感じられる社会です。子どもが安心して成長し、その安心感を大人になっても保ち続けられる社会を目指しています。それが、社会を信じる子どもに育つことに繋がるのだと思います。そして、自殺やいじめなどで命を失う子どもがいなくなる社会を実現したいです」
今西「本日はありがとうございます。山田議員のように子ども政策のために尽力していただける議員は貴重な存在ですね。今後も頑張ってください」
山田「ありがとうございます。今後も子ども達のために頑張ります」
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績