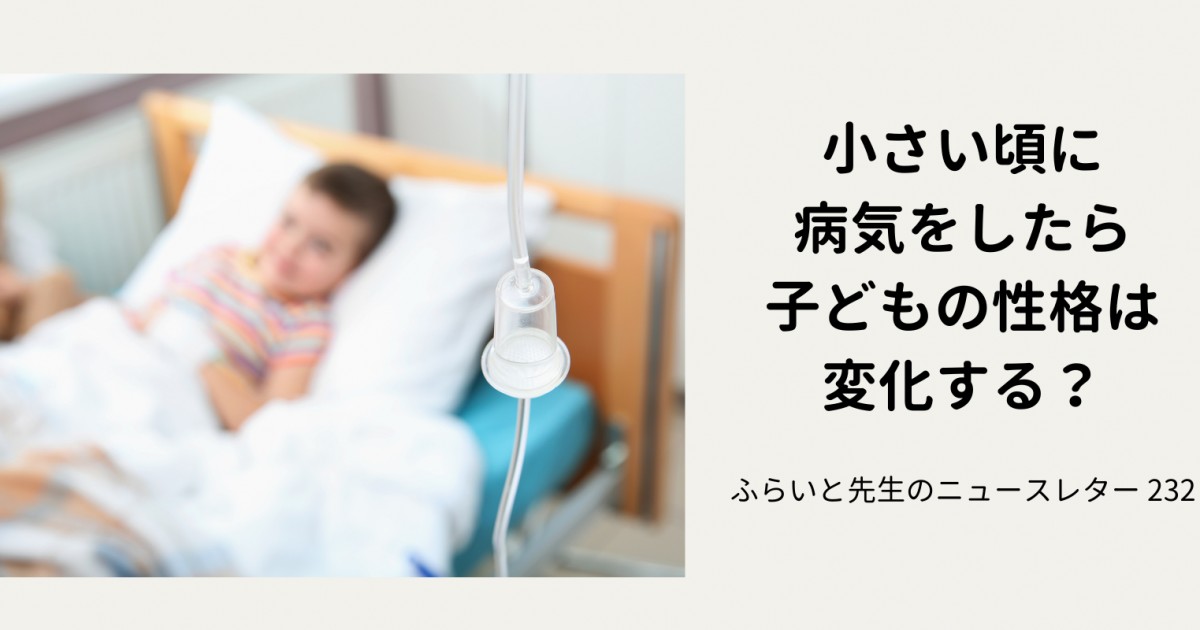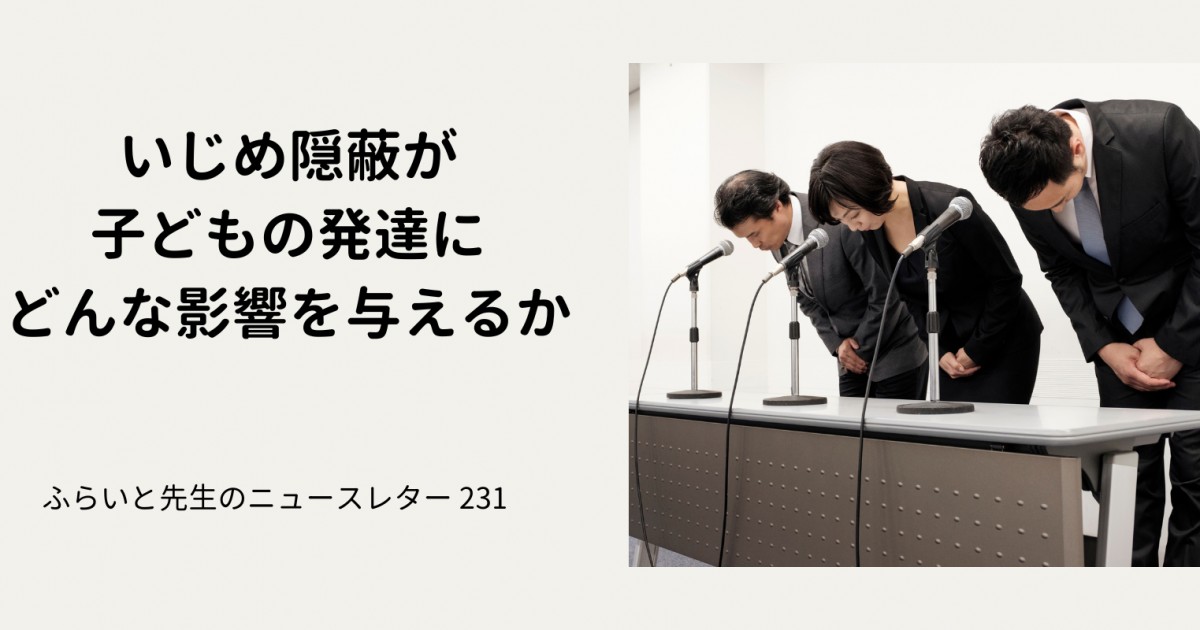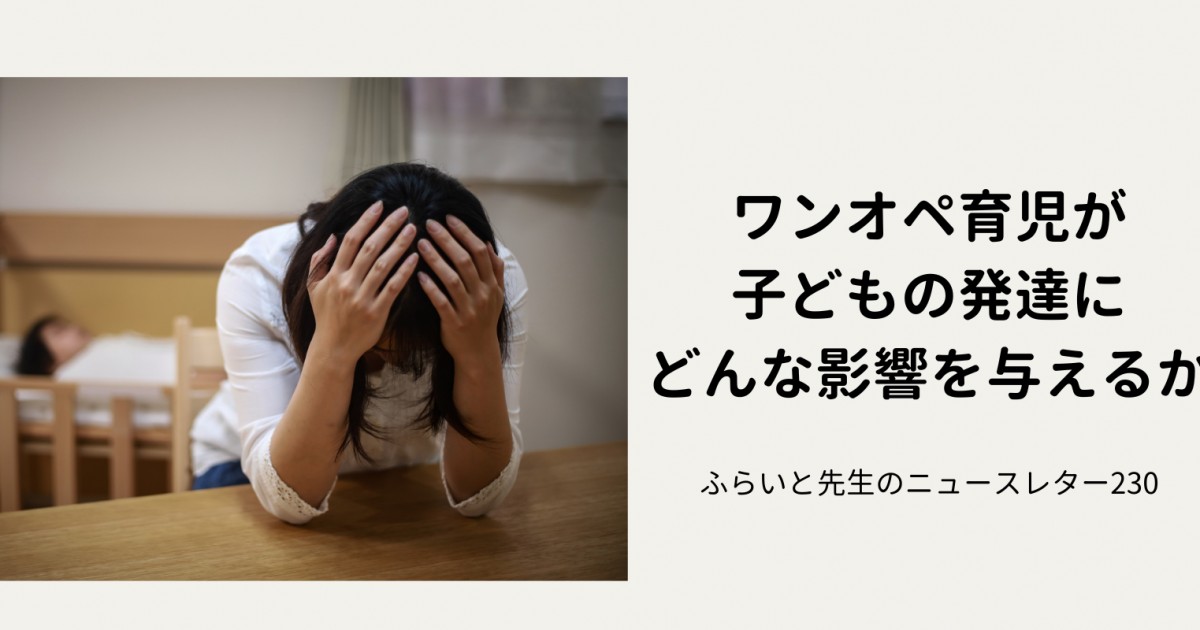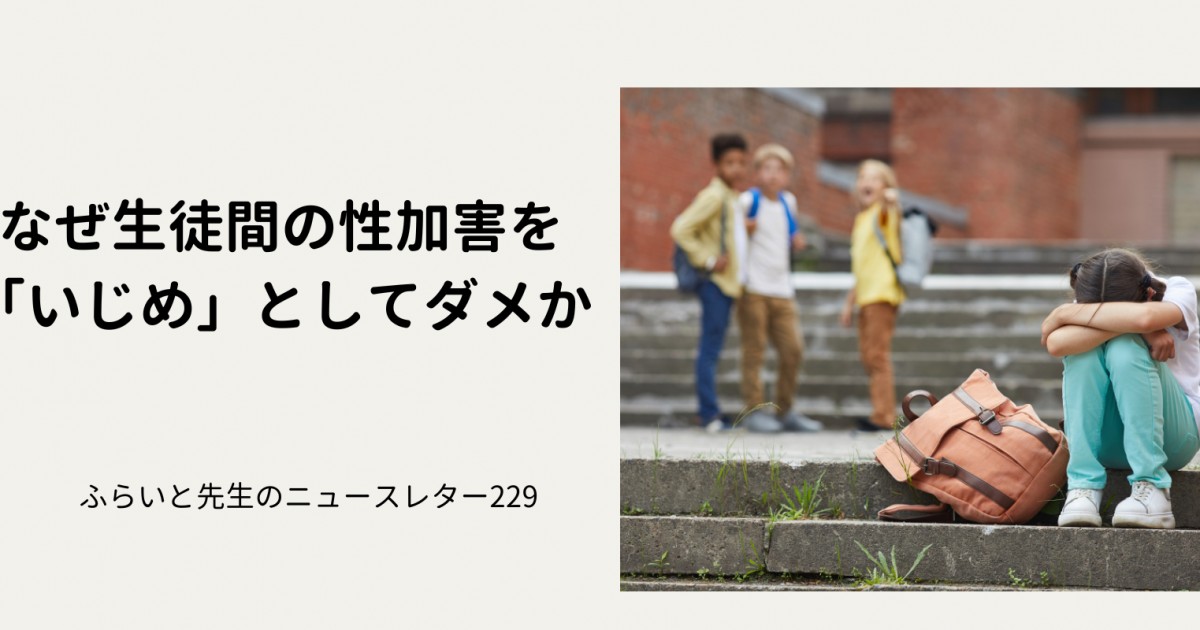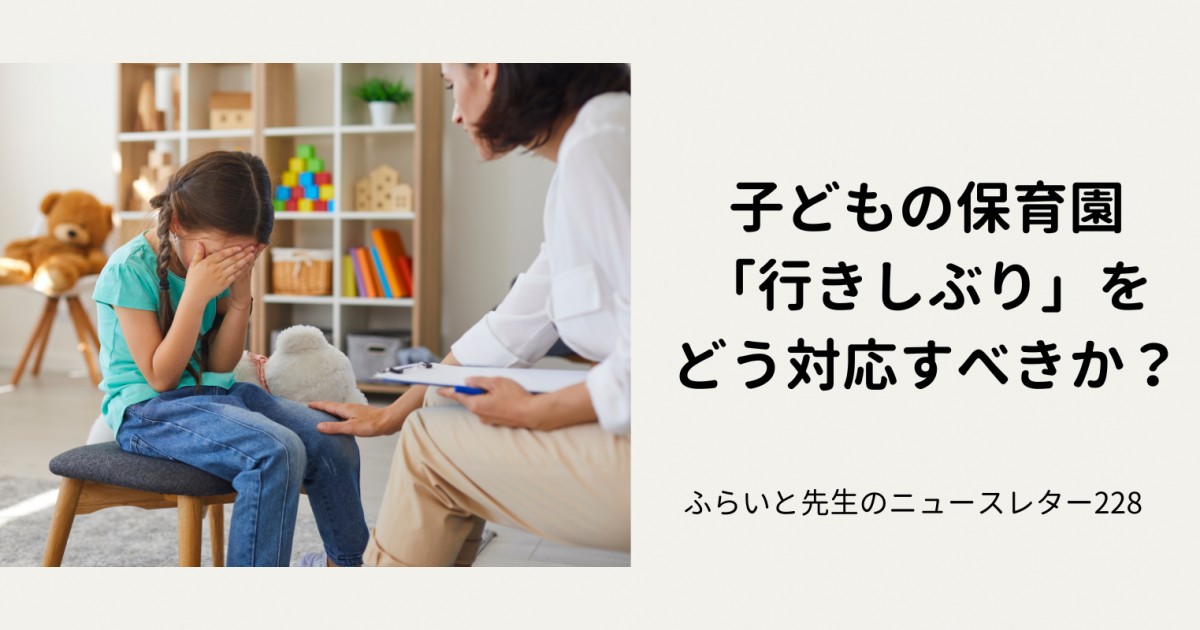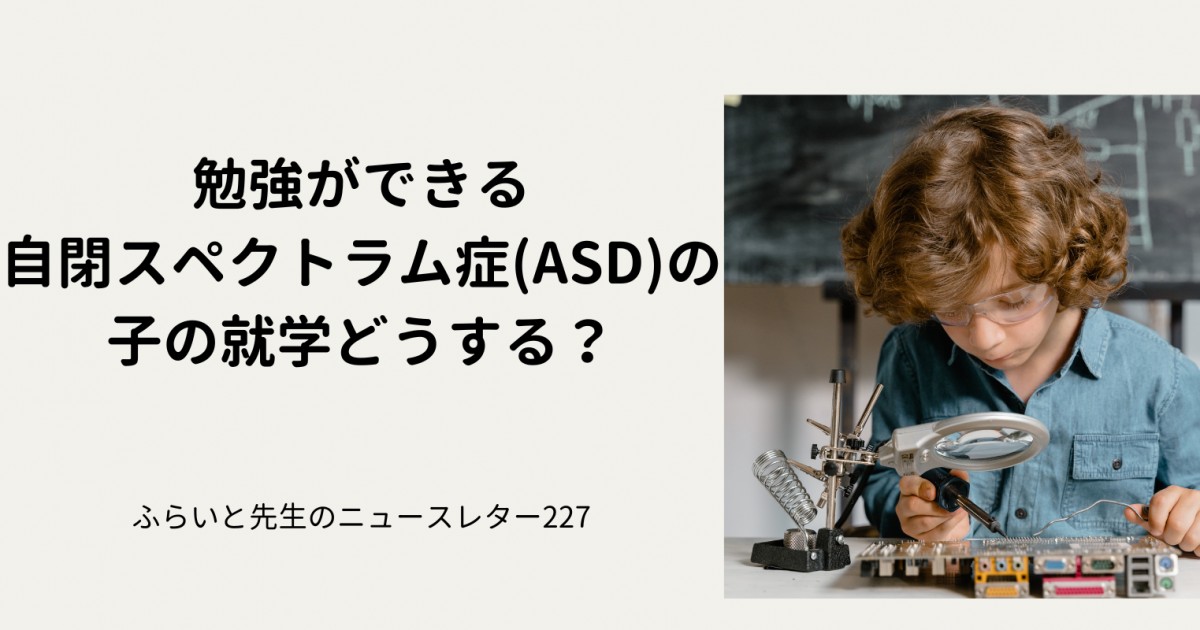「森の幼稚園」は子どもの発達を伸ばす?
皆さん、こんにちは。
8月も終わろうとしていますね。
Q&Aに頂いた質問にお答えするコーナーとても好評です。皆さんから頂いた質問に一つ一つ答えていますが、また新しく質問を頂くのでまた溜まって行くというサイクルになっています。
質問頂けるだけでもありがたい事ですよね。
今回は質問されて確かに自分も気になるなと思ったテーマなので、調べてまとめるのが楽しみです。では今回も書いていきましょう。
ふらいと先生のニュースレターは、子育て中の方が必要な「エビデンスに基づく子どもを守るための知識」を、小児科医のふらいとがわかりやすくお届けしています。
過去記事や毎月すべての「エビデンスに基づいた子どもを守るための知識」を受け取るにはサポートメンバーをご検討ください。今回の記事も登録いただければ最後まで読めます。
告知
Youtube番組のPIVOTに出演しました。このニュースレターで書いている記事が注目され、お声がかかりました。ミュージックステーションの司会だった竹内アナも、元NHKの小手森アナも鋭い質問をたくさんしてきて、子どもを思う良いお母さんだなと感じました。是非お時間ある方は下記リンクからご視聴ください。恐ろしいのはこのPIVOTが配信される度にこのニュースレターの登録者が100人増えた事です。Youtube恐るべし。
しかし、自分の顔パンパンやわ。放送を見てダイエットを始めました。

Vol.1 早期保育と3歳児神話を科学的に検証
Vol.2 毒親に育てられた子どもの末路
いつも楽しくニュースレターを拝読しています。何気ない疑問にもエビデンスを載せたうえて先生の見解も知ることができ、そうだったんだ!と驚くことも少なくないです。いつもありがとうございます。いわゆる「自然派」の保育園・幼稚園と一般的な保育園・幼稚園で、将来的に差が出てくる事はあるのでしょうか?自分は一般的な保育園に子どもをを通わせています。帰省した際に、義姉がいわゆる「自然派」幼稚園に子どもを通わせていると聞きました。その幼稚園では、そもそも園庭という概念がなく周りが森などの自然に囲まれていて、猛暑日でも雨でも毎日外で過ごすそうです。自分の子供が通っている保育園は、もちろん雨では室内遊びですし30℃ほど超える日も熱中症対策のため室内で過ごしています。自分はフルタイムで働いているため幼稚園という選択肢自体が難しいのですが、毎日自然の中で過ごせる環境にあるというのはなかなか魅力的に感じます。このような環境は、将来的な性格や進路に影響を与えることもあるのでしょうか?
ニュースレターをいつも読んで頂き有難うございます。そう言って頂きとても嬉しく思います。
質問もありがとうございました。確かにこの「自然の幼稚園」というのは最近よく耳にしますね。
文中にある「自然派」の保育園・幼稚園という表現だと、ワクチンを打たないとかの「自然派」に勘違いされるのでここでは「森の幼稚園」という表現に変えて解説しますね。
森の幼稚園の歴史
確かに、この「森の幼稚園」最近多いですよね。
実は発達を診療していく中で何度か聞かれたことがあります。
確か幼稚園を選ぶ時に「森の幼稚園の方がいいのですか?」と聞かれたように思います。実際発達に関してはどうなのかはわからなかったので正直に「わかりません」とお答えしましたが・・
森の幼稚園とは自然の中での保育活動を主とする幼稚園・保育園のことで、実は森の幼稚園の普及状況は近年急速に拡大しています。
この自然を大切にする「森の幼稚園」の定義はとても難しくどこまでを定義として入れるのかは難しいのですが、NPO法人森のようちえん全国ネットワークの調査によると、2014年の時点で「森のようちえん」という名称で活動している団体は 全国で250以上に上るとされています。これは自主保育や自然学校、認可外保育も含む広義のカウントなので、正確な数はわかりませんが、自分もこの多さに驚きました(2011年は70箇所という諸説もあり)
自然との触れ合いを重視する森の幼稚園の始まりは1950年代のデンマーク。エラ・フラタウという一人のお母さんが自分の子どもと近所の子どもを森の中で保育し始めたことから始まったと言われています。
その後森の幼稚園は北欧に広がり、1990年代ドイツで環境問題を背景に爆発的に急増します。ドイツの森の幼稚園は、園舎と園庭を持たず、年間通じて毎日森に出かけるスタイルの幼稚園だそうです。自治体の公認となっており、ドイツ全土に400以上あると言われています。
日本では「森の幼稚園」という概念が1990年代に紹介されたことで野外保育の価値が再認識され、広がっていきました。
2005年から、全国の森のようちえん関係者が年に一度集う「森のようちえん全国交流フォーラム」が始まり、2008年には森のようちえんを普及・発展させていく「森のようちえん全国ネットワーク」が設立されました(現在の「NPO法人森のようちえん全国ネットワーク連盟」)(#1)
自然は子どもの発達を伸ばす?
近年、こういった森や野山を主な活動の場とする「森の幼稚園」に代表される、自然に触れ合う幼児教育への関心が高まっていることは事実です。
確かに都市化が進み、子どもたちが自然と触れ合う機会が減っていますよね。
自分の娘達も気づいたらタブレットやテレビ漬けになってしまうので、もう少し外に出て遊んで欲しいものです。
こう言った自然に触れ合う教育方針が子どもの発達に良い影響を与えるのではないかという期待を親なら誰でも抱いてしまうものですよね。
一方で、毎日外で過ごすという環境が、将来の性格や学力、さらには進路にどのような影響を与えるのか、具体的なことは実はあまり知られていません。
特に都市部に住んでいて一般的な保育園や幼稚園を選択している親御さんにとっては、こうした違いが気になるところでしょう。
まず「森の幼稚園が子ども達の発達に良いのか」というテーマを考える前に、そもそも自然が発達にどのような影響を与えるのかを解説していきます。
社会で生きていく上で不可欠な、他者と関わる力や自分自身の心をコントロールする力は「非認知能力」と呼ばれ、幼児期にその土台が築かれます。この非認知機能という言葉は育児をしていれば一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
この森の幼稚園で見られるような自然を基盤とした教育(Nature-Based Early Childhood Education、以下自然教育と呼びます)が子どもの発達を育むことは、多くの研究で示唆されています。
では具体的にどんな能力を育むと言われているのでしょうか?
英国ストラスクライド大学などの研究チームが2022年に発表したシステマティックレビュー(複数の研究を評価した複合的な研究のこと)では、2歳から7歳の子どもを対象とした36件の研究を吟味し、自然教育と社会的スキル、社会的・感情的発達との間に肯定的な関連が見られたと報告しています(#2)。つまり、自然を基本とした教育をすると社会性は高まるし、感情の発達は伸びるとされたのです。
また、米国で行われた別の研究では自然保育園に通う78人の子どもと、一般的な保育園に通う14人の子どもを1年間にわたって追跡調査しました(#3)。その結果、Deveraux Early Childhood Assessment for Preschoolers, Second Edition (DECA-P2)という評価尺度で測定した「主体性」「自己調整」「愛着」といったレジリエンスに関連する保護因子が、自然教育に基づく保育園に通う子どもたちにおいて有意に強化されたことが報告されています。
自分の感情や行動をコントロールする「自己調整能力」や、困難な状況から立ち直る力である「レジリエンス」は、将来の学業成績や社会的な成功と関連のある重要な力と言われています。
自然教育はこういった「自分の感情をコントロールする」力や「苦しい状況から何とか自分で立ち上がる」力を養っている事が示唆されるのです。
さらに、これに留まりません。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績