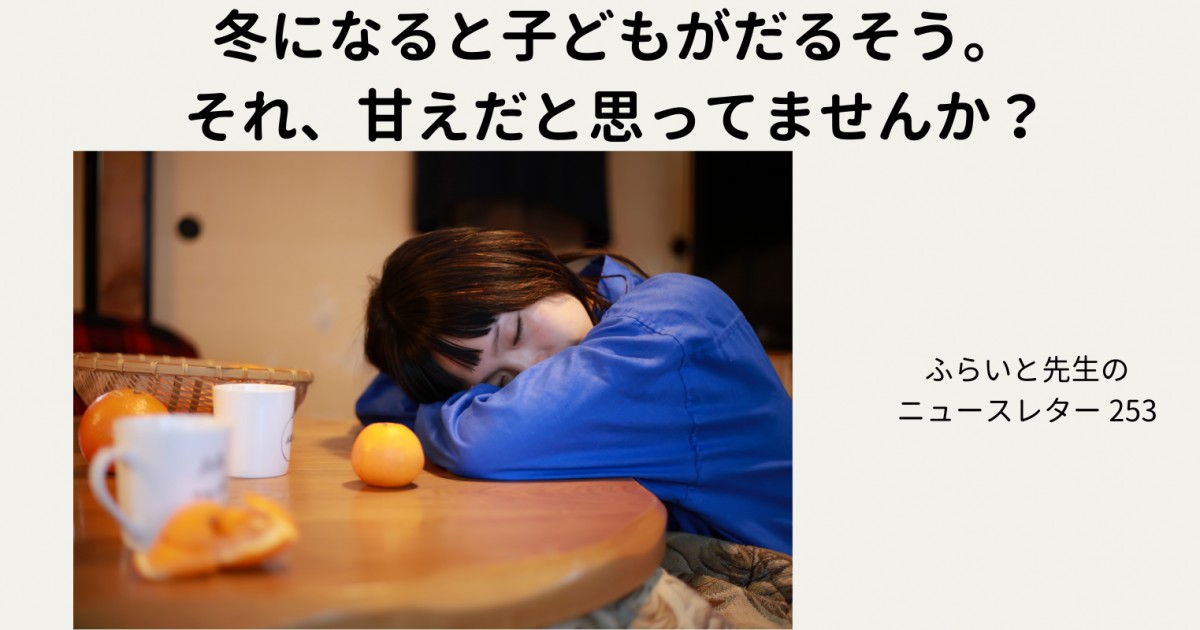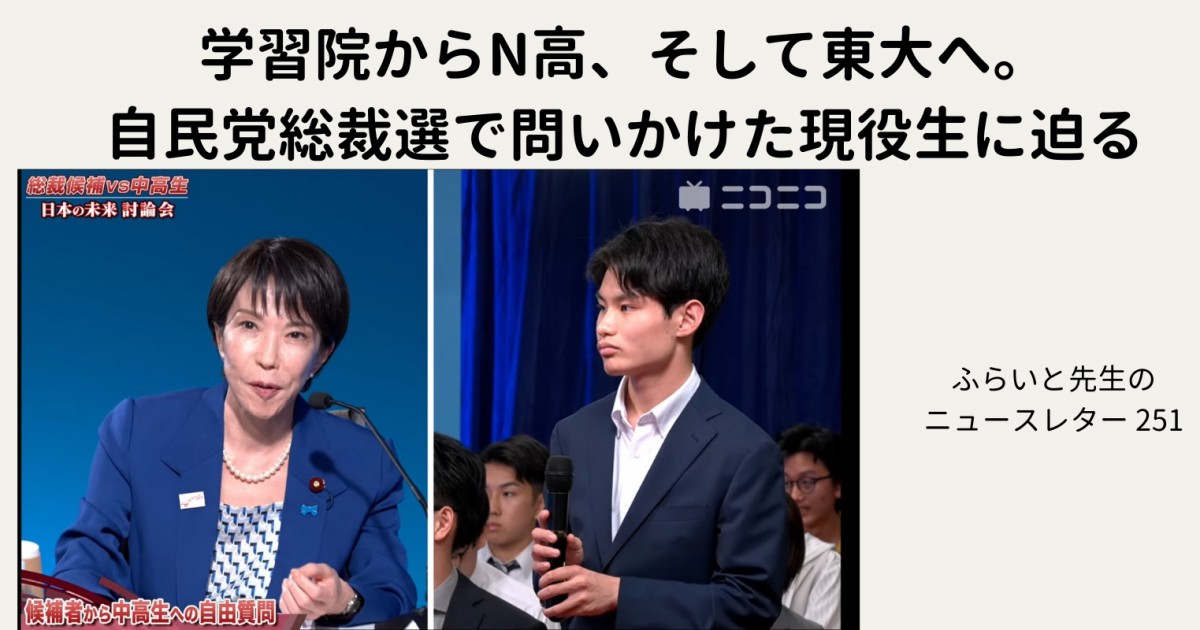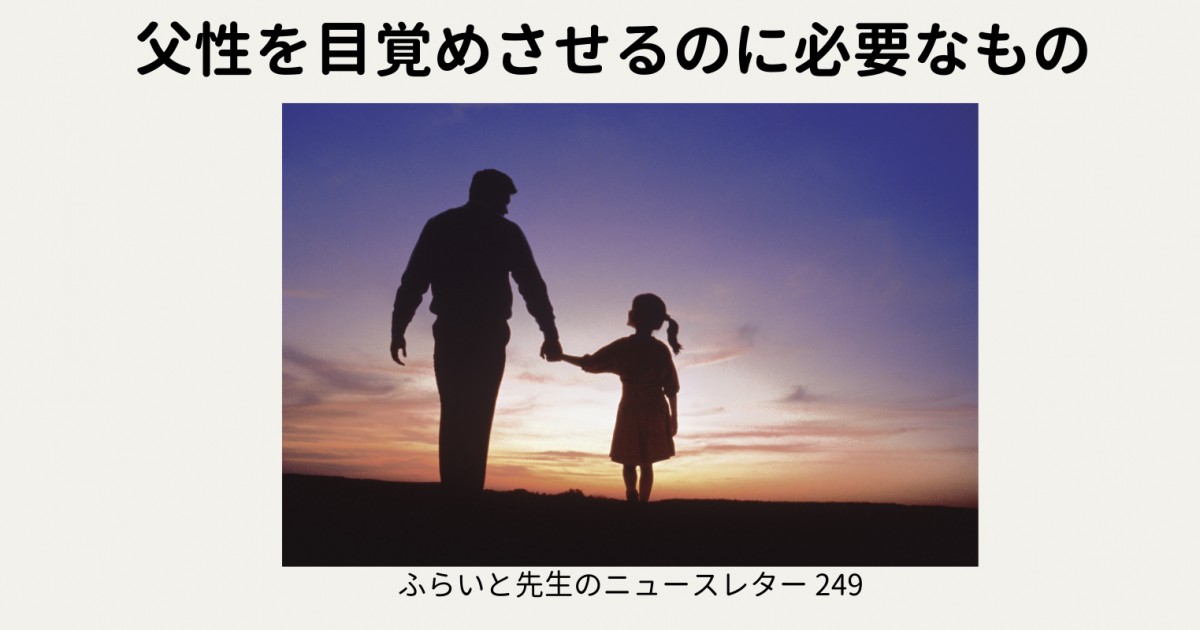「差別意識はないから」という言葉〜書籍と障害者差別の歴史を考える〜
【告知】ニュースレターが本になります!
お世話になってます。本日は告知から入らせてください。
皆様にお世話になっております、このニュースレターが本になります。すでに204個目の記事を迎えたニュースレターを新たに編集し直し、厳選しました。半分が無料記事で、残りの半分は有料記事でその短縮版を載せています。また、本作のために新たに書き下ろしした記事も多数です。本にしませんか?とお話を頂いてから2年もかかってしまいましたが、何とか形にできました。是非、下のリンクからご予約いただけたら幸いです。

ふらいと先生のニュースレターは、子育て中の方が必要な「エビデンスに基づく子どもを守るための知識」を、小児科医のふらいとがわかりやすくお届けしています。
過去記事や毎月すべての「エビデンスに基づいた子どもを守るための知識」を受け取るには有料コースをご検討ください。今回の記事は登録いただければ最後まで読めます。
物議を醸しているある書籍
ある書籍が物議を醸しています。
4月22日に三笠書房から発売される新刊「職場の困った人を動かす心理術」で、ASD(自閉症スペクトラム)、ADHD(注意欠如・多動症)、トラウマ障害、自律神経失調症、鬱病、更年期障害、適応障害、不安障害、パニック障害などを持つ人たちを「『真面目ないい人』を苦しませる、職場の『困った人』たち」として、戦わずして勝つためのテクニックを紹介しています。

なかなかの表現ですが、最も問題となったのはそれらの病気の人達を「動物」に例えている事です。自閉症スペクトラムはナマケモノで、「異臭を放ってもお構いなし」と表現したり、ADHDはサルとして「机の上はまるでゴミ箱」と例えています。
個人的に1番過激だなと思ったのはトラウマ障害をヒツジと例えて「問題が起きたら全て他人のせい」としている事です。トラウマを抱えている人によくこんな表現ができるなあと驚きました。
この表現に対して、SNSでは「差別につながる」などの声が勃発し、まさに炎上。
この騒動に対して、日本自閉症協会も「この書籍は障害に対する誤解を生み、差別や偏見、分断を助長するものと判断します。このような本を、90年を超える歴史がある三笠書房が発刊されることは誠に残念です」という緊急声明を出しました。
一方、この書籍の著者である「カウンセラー」の方もインタビューに答え、障害者を動物に例えた事に対して「差別意識なかった」「愛らしい表現にした」と答えています。
「私の中に差別意識は全くありません。家族に発達障害の傾向があり、私自身の中にもASD、ADHD的な部分、鬱病や愛着障害の芽がある。病気として出ていないだけ。私自身も生きづらさを感じてきました」
そんな中で作画を担当された方が謝罪文を公開しました。私個人としてはこの方の言葉にとても誠意を感じました。
このたび、私が装画を担当した書籍について、批判やご指摘の声が上がっている件について、私個人の立場から経緯と考えを整理し、お伝えいたします。まず、当該装画について差別的な印象を受けたというご意見があることを、真摯に受け止めております。ご不快な思いをされた方がいらっしゃること、それ自体が大きな問題であり、表現に関わった一人として深くお詫び申し上げます。
一方で、書籍はAmazonランキングで発売前にもかかわらず見事11位を獲得しています(4/20時点)。発売前の書籍ではランキングトップとなっています。自分の書籍が現時点で発売前174位ですから大変悔しい結果です(笑)。エビデンスを重視して真っ当な気持ちで本を書いても、差別で問題になっている本の方が売れてしまう悲しい現実を示しています。

これらの事態を受けて、出版差し止めを求めるオンライン署名が4月17日に始まりました。オンライン署名サイト「Change.org」上で、この書籍について「発達障害や精神疾患患者を差別し、社会的排除や分断を招きかねない内容」として、署名が始まっています。
しかし、「書籍と障害者差別の関係」は今に始まったものではありません。私も普段、障害児を診察する立場であり、さまざまな情報を啓発をしている立場として、ここは改めて押さえておく必要があると思い今回の執筆に至ります。障害者差別の本幹とは何なのか、深掘りしていきたいと思います。
漫画ブラックジャック「ある監督の記録」への抗議事件
医学界で「書籍と障害者差別」を語る時に1番出てくるのが、手塚治虫の医療漫画ブラックジャックの連載第153話「ある監督の記録」の中で描かれたロボトミー手術の描写です(#1)。
物語では映画監督の父・野崎が、生まれつき脳性麻痺をもつ我が子の手術をブラック・ジャックに依頼します。野崎監督は息子の闘病記録映画を制作しており、そのクライマックスとして手術シーンを撮影したいという意図でブラック・ジャックを訪ねました。ブラック・ジャックは一度は「くだらんですなぁ」と断りますが、「治せるアテのない手術」であることを理由に法外な手術料と有資格医の助手参加を条件に依頼を引き受けます。劇中で脳性麻痺は通常治せない障害と説明されますが、ブラック・ジャックは過去に偶然にも同様の手術で患者を治せた経験があるとして手術に挑みます。
作中で描かれた手術のシーンでは、ブラック・ジャックが患者の脳の画像を指し示しながら「この中枢にロボトミーで刺激を与えれば機能が正常にもどるきっかけになる」と説明します。つまり患者の運動中枢に対しロボトミー手術による刺激を加えることで、麻痺が治る可能性があると語ったのです。実際に物語の結末では手術と映画撮影は成功し、試写会で青年が回復した姿が観客の称賛を受ける描写になっていたのです。
「ある監督の記録」掲載直後、この内容に対して障害者団体から強い抗議が寄せられました。具体的には、脳性麻痺者の当事者団体である「全国青い芝の会」と、「ロボトミーを糾弾しAさんを支援する会」という二つの団体が連名で手塚治虫および出版社の秋田書店へ抗議文を提出したのです。抗議した障害者グループは「障害者に対する偏見から、(学会でも否定されている)ロボトミーを美化している」とマンガを非難しました。
ロボトミー手術は別名、前頭葉白質切截術とも呼ばれ、実際にかつて精神疾患の治療法として行われていた脳外科手術です。患者の脳の前頭葉の神経回路を切除・切断するもので、1930~50年代には統合失調症など重度の精神疾患に対する画期的療法と考えられていました。
しかし、その後手術による死亡例や、手術後に患者の意志や感情が失われ人格が変化してしまうなど深刻かつ不可逆的な後遺症が多数報告され、ロボトミーは「人間らしさ」を破壊する危険な医療行為だと判明し、各国で強い批判を受けて1960年代までに廃れ、倫理的にも医学的にも実施すべきではない手術と見なされるようになります。日本でも1975年に日本精神神経学会が「精神外科(ロボトミーのような脳手術)は医療としてなされるべきではない」という否定的決議に関するコメントを発表しており、1970年代には事実上施行してはいけない治療法になっていたのです。
いずれにせよ、脳性麻痺は外科手術で根本的に治療できるものではありませんし、当時の医学の見解をもってしても明らかに著しく不適切で誤解を招く内容となりました。
手塚治虫側もこの批判を真摯に受け止め、ただちに非を認め、実際に同作品内容の修正と謝罪が行われました。手塚側は本作品でロボトミーという危険な手術を肯定的に描いてしまったことはもちろんですが、「障害者を健常者に同化させるべき存在として描いたことに対して深い反省と謝罪」を表明しています。これは当時の謝罪としては画期的だったと感じます。
この「ある監督の記録」は後に単行本化される際に大幅な改稿が行われ、タイトルも「フィルムは二つあった」に変更されました。改訂版では患者の疾患設定が脳性麻痺からデルマトミオージス(皮膚筋炎)に変更され、手術内容も脳外科手術ではなく直腸や腎臓の手術に差し替えられています。
このように「ある監督の記録」に対する批判は単なる医学用語の誤りを超えて、医学的に誤った情報の拡散、人権感覚の欠如した治療観、創作における障害者像の偏り、そして社会全体への悪影響といった多角的な問題に及んでいったのが特徴的でした。
障害者差別「ピノキオ」童話回収事件

ピノッキオの冒険の挿絵 Wikipediaより
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績