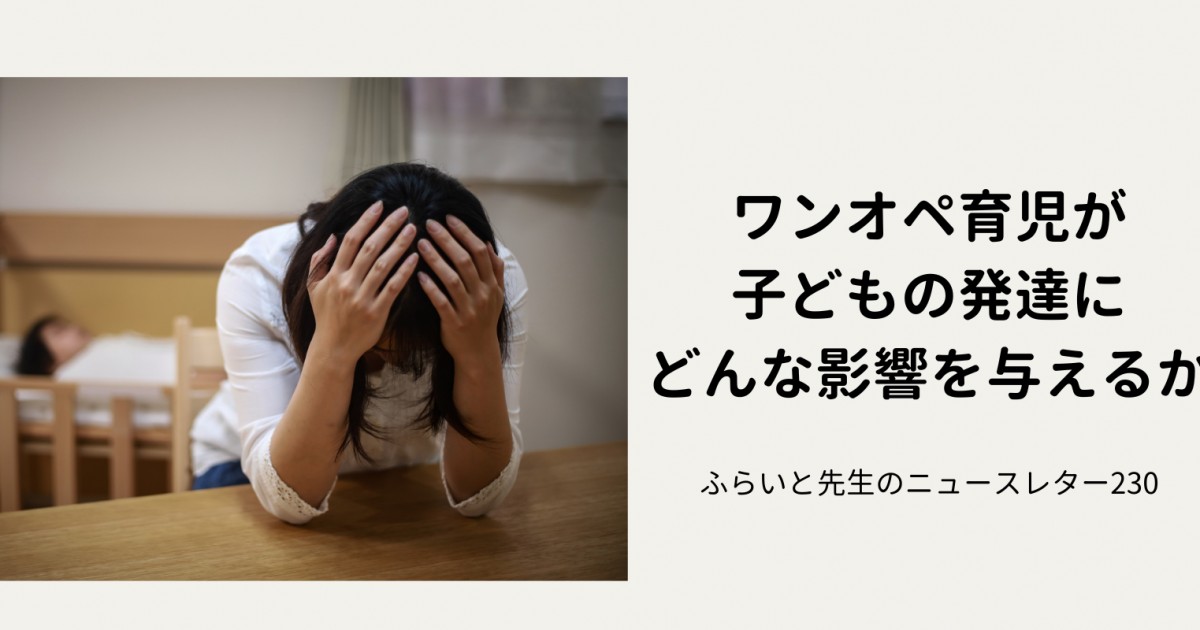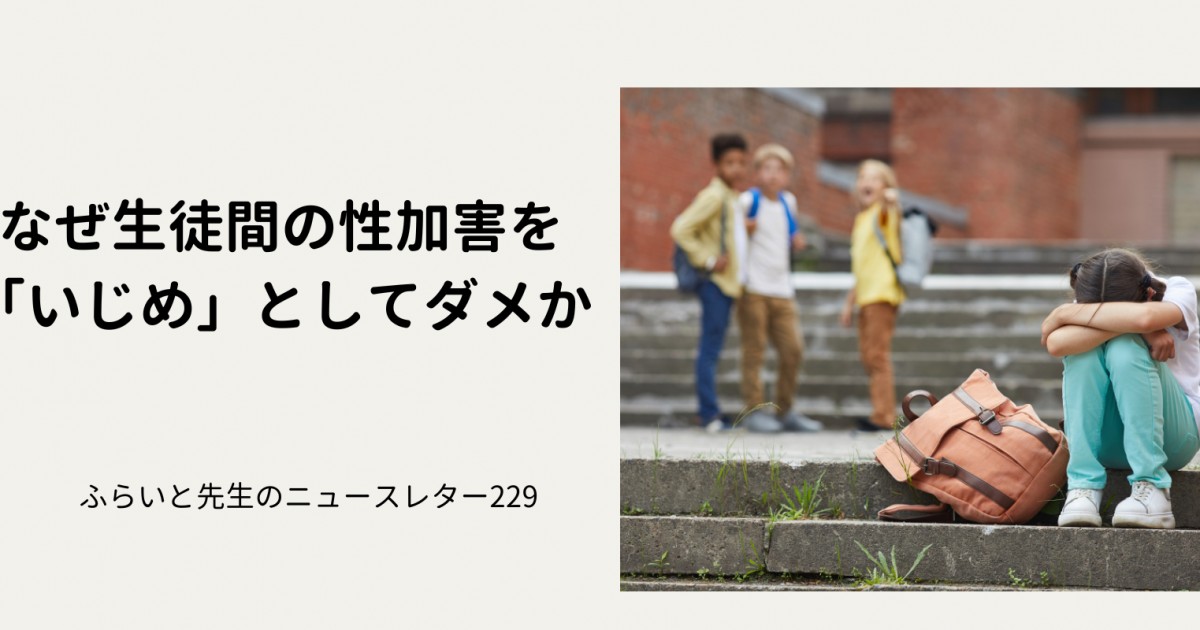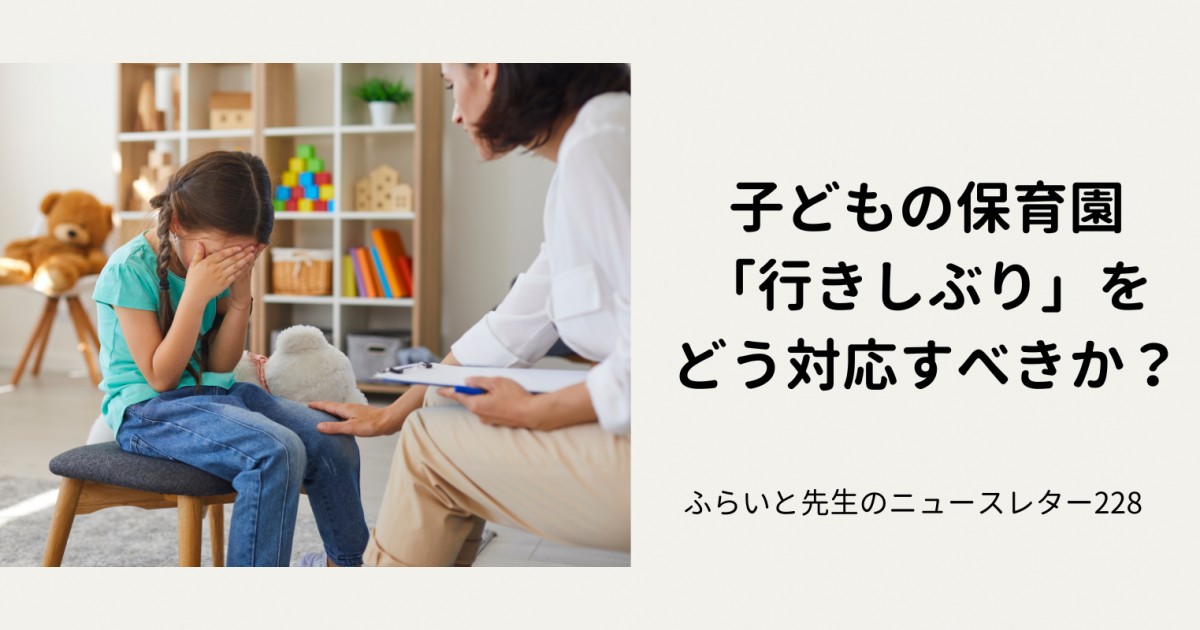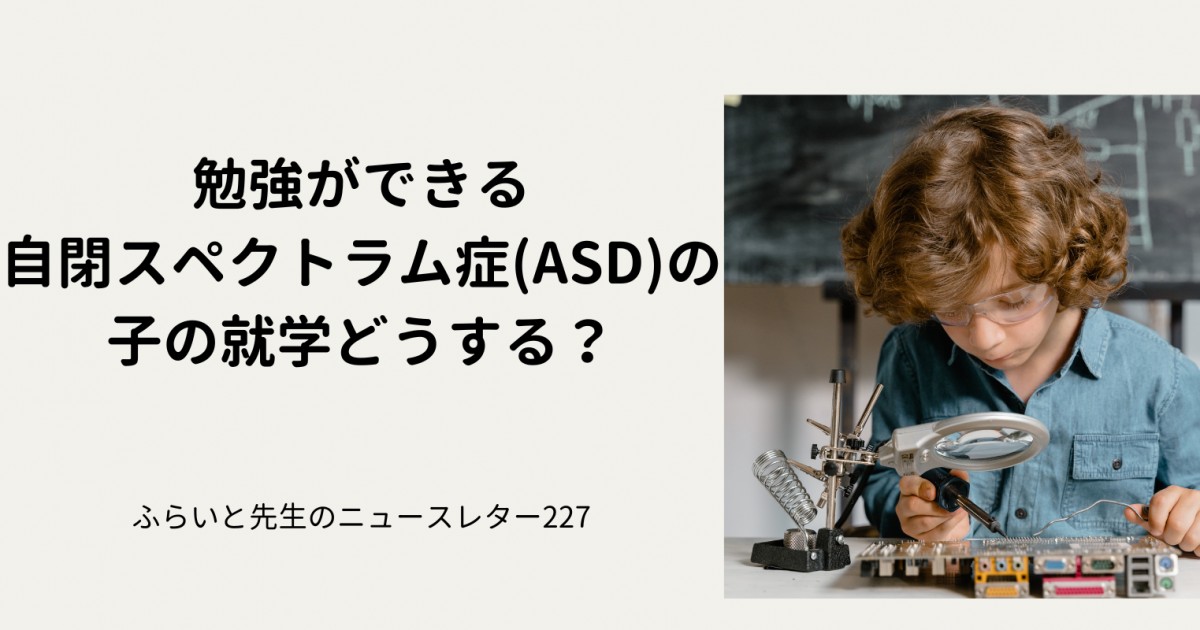こどもの悪意なきウソを親はどう対応すべき?
今回も頂いた質問にお答えします。
今西洋介
2025.05.31
サポートメンバー限定
今回もQ&Aコーナーで頂いたご質問にお答えするコーナーです。
いつもニュースレター配信を楽しみにしております。たまに覗かせる先生の娘さんとの関わりや眼差しに、同じく娘を持つ身として共感しています。今回質問したいのは、子どもの嘘について。本人が嘘をついた自覚がなく、自分の頭の中の想像を現実と思い込んでいる、といったこと、小さいうちはよくあると思います。それが中学生になっても続く場合は、異常なのでしょうか?少し発達障害がある(学習障害がメインでコミュニケーション能力は問題ない)ため定期通院しているのですが、その小児科担当医には実害がないのであれば話を合わせて聞いてあげていれば良いと言われました。指摘すると傷ついて親と話さなくなるかもしれないとも言われました。確かにその嘘も大した話ではなく、誰々が可愛いと言ってくれた、誰々先生が好きなものは◯◯だと言っていた、などというレベルの、いちいち問いただすほどではないけれど、話の登場人物に後日聞いてみると、そんな話はしていない、会っていない…といった感じのものです。実害はないといえばなく、話を盛っているといえば「盛る」範囲内ではあるのかもしれませんが、小さな嘘でも、そのうち人にばれて信頼を失うことになるのではないでしょうか?言った、言ってない問題も怖いです。担当小児科医に最近も相談しましたが、幻覚、幻聴の類でない限り、特に対応はいらないと言われました。とはいえ、娘の精神状態も心配ですし、それをしてしまう心の仕組みもわからないし、その対応もわからないまま今にいたります。親はどうすれば良いのでしょうか?以上、長文失礼いたしました。
思春期のお子さん、特に学習障害のあるお子さんが、実際には起きていないことをまるで本当にあったかのように話す姿を目の当たりにすると、親御さんは心配になりますよね。
その言葉が意図的な嘘ではないにしても、現実と空想の区別がつかなくなっているのではないか、精神状態は大丈夫だろうか、将来的に周囲との信頼関係を築いていけるだろうか、といった不安が頭をよぎるのは当然だと思います。
ここでは当然、医学的な個人相談はできないので、あくまでも一般的なお話をしていこうと思います。
お子さんの言葉が本当かどうかわからないとき、その嘘は意図的に人を欺こうとする行為ではないかもしれません。
医学的には「作話(confabulation)」と呼ばれる現象が考えられます。
作話とは、悪意や騙す意図なしに、実際には体験していないことや誤った記憶を、本人が真実であると信じ込んで話したり、行動したりする状態を指します。作話をする人は、自分の話が作り話であるという自覚がなく、むしろそれを現実の出来事だと確信していることが多いのが特徴です(#1)
子どもの作話と意図的な嘘との見分けかたは、その「意図」にあります。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績