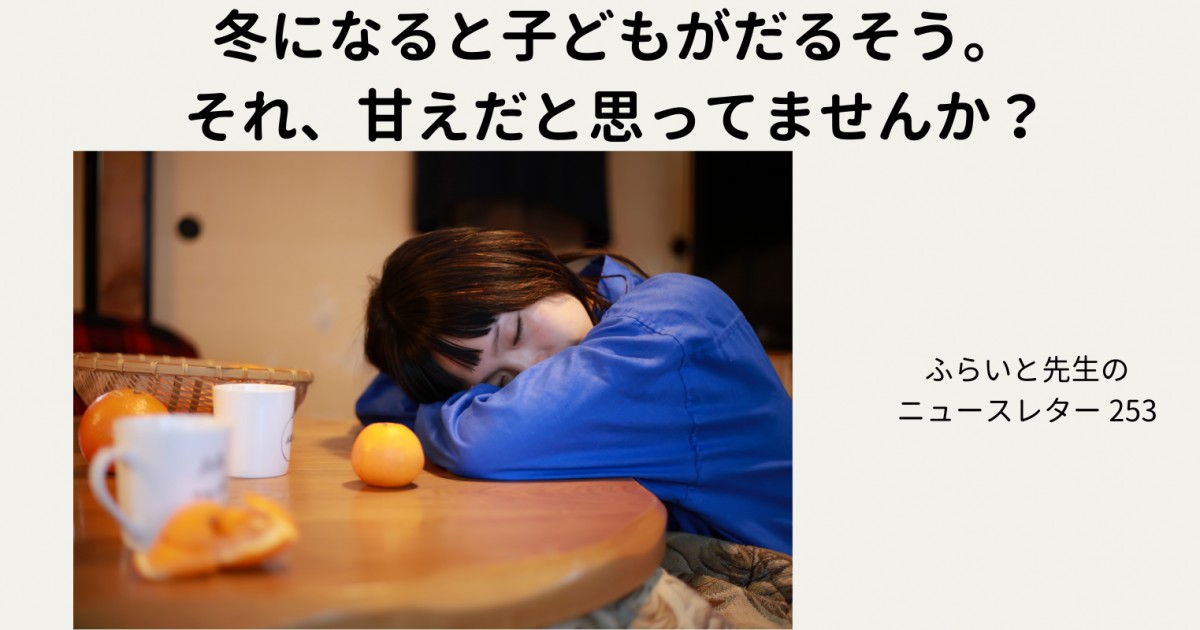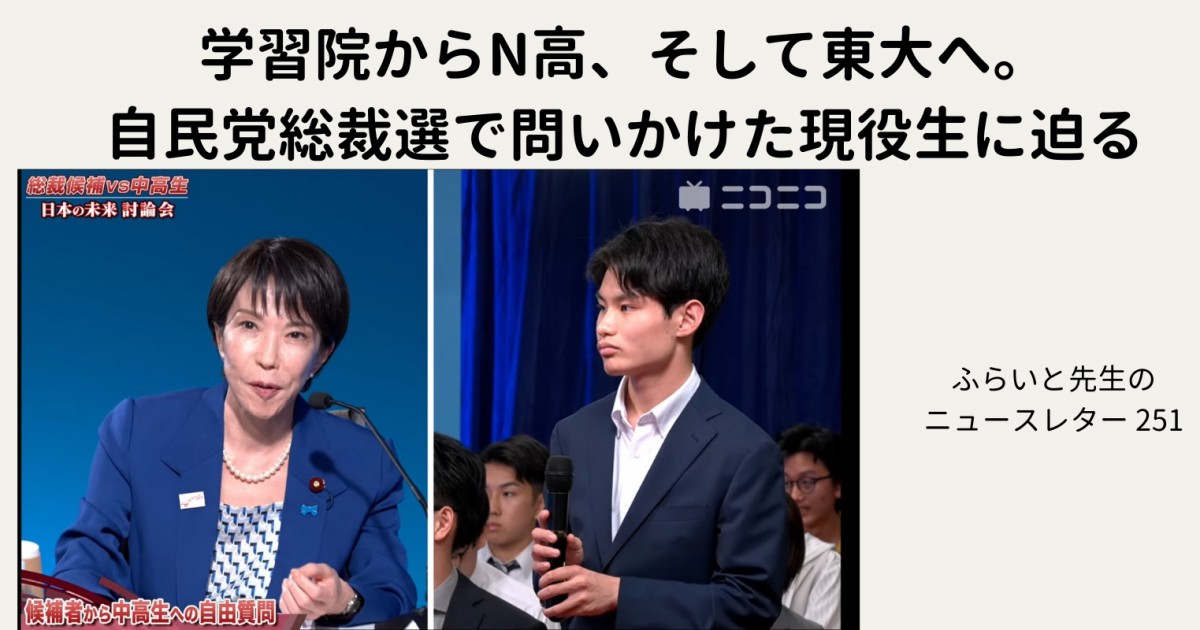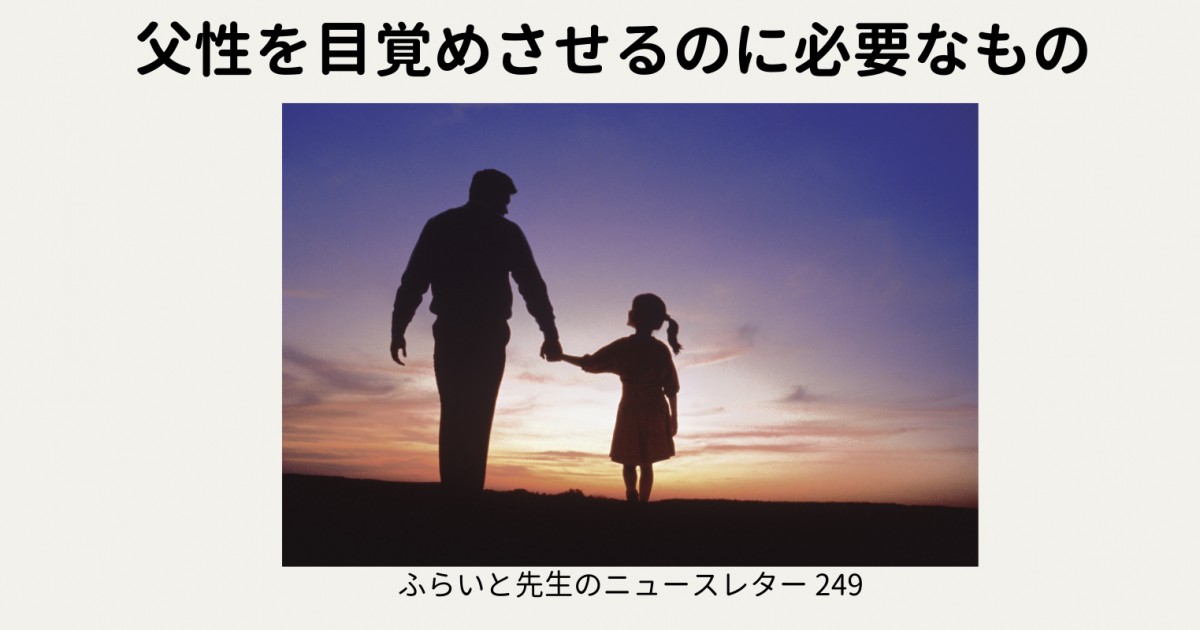米国の赤ちゃんボックスを見て、考える
新年度始まりましたね。日本はきっと桜がきれいですよね。
今年度もこのニュースレターをコツコツと届けようと思っていますので宜しくお願いします。ニュースレターと言う媒体は一見、Web記事と同様に記事を一方的に届けると思われがちですが、自分はそう思っていません。この媒体こそ読者の皆さんとの「双方向性」が何より大切だと感じています。もちろん記事を届けるのもベースにあるのですが、記事を元に頂いたコメントでのやり取りや、Q&Aコーナーで質問募集をしてそれに答えるなどの双方向性が生まれるのが醍醐味と感じています。今年度も一方的にならないように注意しながら、進めていきたいと思います。
また自分が記事を執筆し続けられるのもサポートメンバーの皆様の援助があってこそです。本当に感謝しております。近日中にサポートメンバー限定の企画も考えておりますので、楽しみにしていて下さい。
ふらいと先生のニュースレターは、子育て中の方が必要な「エビデンスに基づく子どもを守るための知識」を、小児科医のふらいとがわかりやすくお届けしています。
過去記事や毎月すべての「エビデンスに基づいた子どもを守るための知識」を受け取るには有料コースをご検討ください。今回の記事はメールアドレスのみ登録いただければ最後まで読めます。
東京都で始まった「いのちのバスケット」
注意;この記事内ではわかりやすさを重視して便宜上「赤ちゃんポスト」と表現しますが、この赤ちゃんポストと言う表現に賛同しているわけではないので、その点はご了承ください。
様々な理由で親が出産後に育てられない子どもを匿名で預かる赤ちゃんポスト。
日本では熊本の慈恵病院しか行われていませんが、今週3月31日から東京・墨田区の社会福祉法人・賛育会の賛育会病院が「赤ちゃんポスト」を新たに運用開始することが発表されました。対象は生後4週間以内で、同病院は産科や小児科を内設し地域周産期医療センターにも指定されているようです。
尚、名前は赤ちゃんポストという名称ではなく、「いのちのバスケット」だそうです。ポスト📮と言われると無機質な感じがして自分的には少し抵抗感があったのですが、いのちのバスケットはまだ温かみを感じて、名前もその通りだなと共感できるところもあります。
また、妊婦が医療機関以外に名前など身元を明かさずに出産する「内密出産」の事業も同時に開始することが発表されました。問題は、同日に慈恵病院の記者会見でも指摘された通り、賛育会病院は内密出産が全額自費である事でしょう。内密出産を頼る女性達は孤立していて金銭的にも厳しい状況に置かれていますから、全額自費だと彼女達が頼る可能性は低いと考えられます。
とは言え、自分もNICUで親が育てられないと、遺棄されたり傷つけられたりした赤ちゃん達を多く見てきましたから、やはり赤ちゃんポストが増えてくれる事自体はありがたい事だなと思っています。
早速、東京都でも賛育会病院の取り組みを検証するため、医療関係者、児童福祉関係者、弁護士などの有識者で構成する検証部会を設置すると発表しました。東京都江東区の児童相談所が24時間体制で対応するそうです。
今後もこの動きは注視していく必要があると思われます。
米国でのシステム
さてここで皆さんに一つの地図をお見せしましょう。これはカリフォルニア州のロサンゼルス近郊の地図です。ロサンゼルスと言っても東京都23区の2倍の広さはあるのでかなり広大なのですが、この青い点にご注目ください。
この青い点は何を表しているでしょうか?

これは「Safe Surrender Site」を指しています。つまり、親が生後間もない乳児を匿名で安全に引き渡せる場所です。欧米の先進国では、新生児を安全に匿名で託す仕組みとして、国や地域ごとに赤ちゃんポスト(ベビーボックス)または安全な引き渡し制度が存在します。その設置目的は共通して「望まない妊娠に直面した母親が乳児を遺棄したり殺害したりする悲劇を防ぎ、子どもの命を守る」ことにあります。
最初にこの地図を見た時はその多さに大変驚きましたが、これはカリフォルニア州の法律で認められている制度のようですから、この数には納得です。このロサンゼルスには2004年の設立時点で郡消防局の全157消防署とロサンゼルス市消防局の全103消防署が安全な引き渡し場所として指定されていました。これらに郡内の全病院救急部を加えると、ロサンゼルス内の指定施設数は数百か所規模になります。実際、同プログラム開始以来250人以上の乳児がロサンゼルス郡で安全に引き渡されている実績があるようです(#1)
背景には、先ほど私が記載したように若年妊娠や貧困、性的暴力など様々な事情で親が育児放棄に追い込まれるケースがあり、そうした親子を救済する最後の手段として導入されています。
欧米諸国の制度には大きく2種類あり、民間や病院による赤ちゃんポストの設置と、公的な「安全な避難所(Safe Haven)」法による病院・消防署等での引き渡しが挙げられます。いずれも利用に際して親の匿名が保障され、法律上の罪に問われないよう配慮されています。
日本では赤ちゃんポストが広く議論されていますが、後者はあまり知られていません。
安全引渡し指定所
さて話は変わりますが、自分は毎日昼にランニングをする事が日課です。昼食を終えた後に30分だけおおよそ5km走り込むのは非常に気持ちが良くて、頭がスッキリします。特に海もあれば気候も穏やかなので、走りやすい場所に住んでいます。
ある日ランニング中に自宅から徒歩1分の所にある消防署の前を通りかかった時のことです。こんなマークが貼ってありました。


おや?
この真ん中はあの有名なSafe Surrender Siteでは?日本語で言うところの「安全引渡し指定所」ですね。こんな家の近所、しかも毎日通るランニングコースにあるとは!と驚きましたが、急いで自分の職場のIDカードを取りに行き、消防署の玄関でチャイムを鳴らしました。
すると受付のお姉さんと屈強な消防隊員が出てきました。彼らに「自分は日本の小児科医で研究者として今米国にいる。知見を得るためにもSafe Surrender Siteを見せてほしい」と依頼をしました。
すると「OK, doctor!」と快く引き受けてくれました。
ちなみにここは先ほど説明した通り、民間や病院による赤ちゃんポストの設置と、公的な「安全な避難所(Safe Haven)」法による病院・消防署等での引き渡しの2種類がありますが、ここは後者です。
屈強な消防隊員はピーターさんと言うお名前で、消防士21年目のベテランだそうです。握手した手は米国人男性特有の大きくて柔らかいのが印象的でした。
ピーターさんが早速見せてくれたのは「Newborn safe surrender kit」と言うものでした。赤ちゃんが実際に預けられた時に使用する一式のセットですね。

この中には手続き上のマニュアル、郵送用封筒、赤ちゃん側につけるブレスレットと預けた親側に預けるブレスレット、そして赤ちゃん側の医学的な問題がないかの質問票、fact sheetが含まれています。
実際の手順は以下の黄色の紙に示されています。ここで大事な事は「手続きを淡々と進める事」と彼は言っていました。つまり赤ちゃんを受け入れた際に「Do not the judgemental」と書かれているように預けた親に対して現場でジャッジをするなと言う事です。設立当初は預けられた直後に説教をしたり、説得しようとしたりする現場の人間がいてうまく手続きがなされなかったようです。
聞いていいのは赤ちゃんと家族の医学的情報のみです。先ほどのセットに含まれる質問票に基づいて記入してもらいます。

あとは出生後72時間以内と区切りはつけていますが、それより超えて預けられても基本的に預かるそうです。それは出産後のパニックで正確な出生時間がわからないケースに対応してのこと。

もちろん、預けられた後はこちらから病院と密にコンタクトを取り、医学的に受診する必要があるか等を判断していくようです。私も日本の赤ちゃんポストの議論には必ず口を酸っぱくして言っていますが、医療機関特にNICUや小児科との連携は非常に大切です。
なぜなら質問票の1問目にあるように35週以下の早産で産まれているかもしれませんし、6、7問目のようにダウン症などの染色体異常を抱えているケースや心臓の病気を抱えているケースだってあります。これは非医療者では非常に難しく、総合的に判断していく必要があります。

このブレスレットは赤ちゃん側につけられるもの。非常に生々しいです。この同じ番号の書いたブレスレットは預けた親側にも与えられます。そして14日間の間ならばこのブレスレットを頼りにいつでも赤ちゃんを取りにこれるようです。
最後に、ピーターさんに「この制度の運用資金はどうなっているのか」と聞きました。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績